五十肩の痛み方、症状別鍼灸治療法!夜も眠れない激痛、しびれを根本改善
- 鍼灸院 横浜文庫
- 3月27日
- 読了時間: 13分

夜も眠れないほど辛い五十肩の痛み、腕が上がらない、動かしにくいといったつらい症状にお悩みではありませんか?
五十肩は、加齢とともに肩関節の周囲に炎症が起こり、激しい痛みやしびれを伴う疾患です。その痛みは生活の質を著しく低下させ、睡眠不足や日常生活の動作にも支障をきたすことがあります。
本記事では、五十肩の症状や原因、痛みの種類を詳しく解説し、それぞれの症状に合わせた鍼灸治療法をご紹介します。
五十肩の痛みは、急性期、慢性期、炎症期など、段階によって症状が変化するため、適切な治療法を選択することが重要です。鍼灸治療は、肩関節周囲の筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、痛みやしびれを根本から改善へと導きます。
さらに、日常生活での注意点や、睡眠時の姿勢、入浴方法、運動療法についても解説することで、五十肩の痛みを早期に緩和し、快適な日常生活を取り戻すためのお手伝いをします。
この記事を読めば、五十肩に関する正しい知識と、鍼灸治療による効果的な改善策を理解し、痛みや不安から解放されるための第一歩を踏み出せるでしょう。
1. 五十肩とは?

五十肩は、正式には肩関節周囲炎と呼ばれ、肩関節とその周辺組織に炎症や痛みを生じる疾患です。40代から50代に多く発症することから五十肩と呼ばれますが、30代や60代以降で発症することもあります。
明確な原因は特定されていませんが、加齢による肩関節の老化や、肩の使い過ぎ、外傷、糖尿病、甲状腺疾患などが発症に関与していると考えられています。
肩の痛みや運動制限が主な症状で、日常生活に支障をきたすこともあります。自然に治癒するケースもありますが、適切な治療とリハビリテーションを行うことで、より早く症状を改善し、後遺症を残さずに治すことが可能です。
1.1 五十肩の症状
五十肩の症状は大きく分けて、痛み、運動制限、関節の拘縮の3つに分類されます。
痛みは、肩関節周囲の鈍痛、鋭い痛み、焼けるような痛みなど、様々な形で現れます。初期には動かす時だけ痛みますが、症状が進行すると安静時や夜間にも痛み、睡眠に支障をきたすこともあります。また、腕を特定の方向に動かすと痛みが強くなる場合もあります。
運動制限は、腕を上げたり、回したりする動作が困難になることを指します。服を着替えたり、髪を洗ったり、高いところに手が届かなくなるなど、日常生活に大きな影響を与えます。
関節の拘縮は、関節が硬くなって動きにくくなる状態です。長期間適切な治療を行わないと、関節が拘縮し、肩の可動域が狭まってしまうことがあります。
症状 | 詳細 |
痛み | 安静時痛、運動時痛、夜間痛、焼けるような痛み、鋭い痛みなど |
運動制限 | 腕を上げられない、回せない、後ろに回せないなど |
関節の拘縮 | 関節が硬くなり、可動域が制限される |
1.2 五十肩の原因
五十肩の明確な原因は解明されていませんが、加齢に伴う肩関節周囲の組織の変性や、血行不良、肩への負担などが関係していると考えられています。具体的には、肩関節周囲の腱や靭帯、関節包などの組織が炎症を起こしたり、厚くなったり、癒着することで、痛みや運動制限が生じるとされています。
また、糖尿病や甲状腺機能低下症などの基礎疾患がある場合、五十肩を発症しやすくなるという報告もあります。
さらに、肩を酷使する仕事やスポーツ、外傷なども五十肩の原因となることがあります。日常生活における姿勢の悪さや、長時間のデスクワークなども、肩への負担を増やし、五十肩のリスクを高める要因となります。
1.3 五十肩になりやすい人
五十肩は、40代から50代に多く発症しますが、特定の条件下ではより発症リスクが高まると言われています。例えば、デスクワークや手作業など、同じ姿勢を長時間続ける人は、肩関節周囲の筋肉が緊張しやすく、血行不良を起こしやすいため、五十肩になりやすい傾向があります。
また、糖尿病や甲状腺機能低下症などの基礎疾患を持つ人も、五十肩のリスクが高いと言われています。さらに、過去に肩を脱臼したり骨折したりした経験がある人は、肩関節の不安定性や組織の損傷により、五十肩を発症しやすくなる可能性があります。
女性ホルモンの減少も五十肩の発症に関連があると考えられており、閉経後の女性は特に注意が必要です。
加えて、ストレスや冷え性なども、血行不良を促進し、五十肩の症状を悪化させる要因となる可能性があります。これらの要因に心当たりのある方は、日頃から肩のケアを意識し、早期発見・早期治療に努めることが大切です。
2. 五十肩の痛みの種類

五十肩の痛みは、その進行度合いによって大きく変化します。症状の時期に合わせた適切なケアが重要となるため、まずはご自身の痛みがどの種類に当てはまるのか理解しておきましょう。
2.1 急性期:夜も眠れない激痛
五十肩の初期段階である急性期は、突然の激痛に襲われるのが特徴です。特に夜間や安静時に痛みが強まり、睡眠を妨げることもあります。炎症が強く出ている時期でもあるため、肩に触れるだけでも強い痛みを感じることがあります。
2.1.1 夜も眠れない激痛に対する特徴
安静時や夜間に痛みが強まる
肩に触れると激痛が走る
炎症による熱感や腫れを伴う場合もある
痛みのあまり、眠れない日が続く
2.2 慢性期:腕が上がらない、動かしにくい
急性期を過ぎると、強い痛みは徐々に和らいできますが、肩関節の動きが制限されるようになります。腕が上がりにくい、後ろに手が回らないといった症状が代表的です。日常生活にも支障が出始めるため、焦りや不安を感じやすくなります。
2.2.1 腕が上がらない、動かしにくい症状に対する特徴
肩関節の可動域制限
日常生活動作の制限(着替え、髪を洗う、高いところの物を取るなど)
痛みは鈍痛だが、特定の動作で増悪する
肩の筋肉の硬直、萎縮
2.3 炎症期:熱感や腫れを伴う痛み
五十肩は炎症を伴う疾患です。急性期に特に顕著ですが、慢性期にも炎症が再発することがあります。肩に熱感や腫れが見られる場合は、炎症期の特徴的な症状です。安静にしていてもズキズキと痛むこともあります。
2.3.1 熱感や腫れを伴う痛みへの特徴
肩関節周囲の熱感
肩関節の腫脹
皮膚が赤みを帯びる場合もある
安静時痛
2.4 五十肩に伴うしびれの症状
五十肩では、肩の痛みだけでなく、腕や手、指先にしびれが生じることもあります。これは、肩関節周囲の炎症や筋肉の緊張が、神経を圧迫するために起こります。しびれの程度は、軽度なものから、強い痛みを伴うものまで様々です。
2.4.1 しびれの症状に対する特徴
腕、手、指先のしびれ
ジンジンとした感覚、灼熱感
夜間や安静時にしびれが増悪する
肩の動きに伴ってしびれが変化する
痛みの種類 | 時期 | 主な症状 |
急性期 | 発症初期 | 夜間や安静時の激痛、肩に触れることによる痛み |
慢性期 | 急性期以降 | 肩関節の可動域制限、腕が上がらない、動かしにくい |
炎症期 | 急性期、慢性期を通して起こりうる | 肩関節の熱感、腫れ、安静時痛 |
しびれ | 急性期、慢性期を通して起こりうる | 腕、手、指先のしびれ、ジンジンとした感覚、灼熱感 |
これらの痛みの種類は、必ずしも順番に進行するとは限りません。急性期と慢性期を繰り返したり、炎症期が突発的に起こることもあります。
ご自身の症状を正しく理解し、適切な対処をすることが重要です。五十肩の痛みでお悩みの方は、鍼灸院への相談も検討してみましょう。
3. 症状別鍼灸治療法

五十肩の痛みやしびれに対し、鍼灸治療は症状に合わせた的確なアプローチが重要です。ここでは、五十肩の各段階における鍼灸治療法について詳しく解説します。
3.1 急性期の鍼灸治療
3.1.1 夜も眠れない激痛に対する鍼灸治療
急性期は炎症が強く、痛みが激しい時期です。この段階では、局所の炎症を抑え、痛みを緩和することが最優先となります。主に、痛みを感じている部位周辺のツボに鍼を浅く刺入する手法を用います。鎮痛効果のあるツボとして、肩閠、天宗、秉風などが挙げられます。これらのツボに鍼やお灸を用いることで、局所の血流を改善し、炎症物質の排出を促進します。また、副交感神経を優位にすることで、リラックス効果を高め、痛みの緩和を目指します。
3.2 慢性期の鍼灸治療
3.2.1 腕が上がらない、動かしにくい症状に対する鍼灸治療
慢性期になると、痛みは軽減してきますが、肩関節の動きが制限され、腕が上がりにくくなります。
この時期の鍼灸治療は、肩関節周囲の筋肉の緊張を緩和し、関節可動域の改善を目標とします。肩髎、肩井、巨骨などのツボに鍼を刺入することで、肩甲骨や上腕骨の動きをスムーズにする効果が期待できます。また、お灸を用いることで、温熱効果により筋肉の緊張を和らげ、血行を促進します。
これらの治療に加え、ご自宅でできる簡単なストレッチや体操を指導することで、より効果的な改善を目指します。
3.3 炎症期の鍼灸治療
3.3.1 熱感や腫れを伴う痛みへの鍼灸治療
炎症期は、肩関節に熱感や腫れを伴う痛みが生じます。この段階では、炎症を抑え、痛みを軽減することが重要です。急性期と同様に、阿是穴と呼ばれる痛みのある部位に直接鍼を刺入する手法を用います。また、曲池、外関などのツボに鍼やお灸を用いることで、炎症を抑え、免疫機能を高める効果が期待できます。炎症が強い場合は、患部を冷やすことも効果的です。アイスパックなどで患部を15~20分程度冷やすことで、炎症の悪化を防ぎます。
3.4 五十肩のしびれに対する鍼灸治療
五十肩では、肩や腕、手先にしびれが生じることもあります。これは、肩関節周囲の筋肉の緊張や炎症によって神経が圧迫されることが原因と考えられます。
しびれに対する鍼灸治療では、圧迫されている神経の走行に沿って、天柱、風池、手三里などのツボに鍼を刺入します。これにより、神経の圧迫を解放し、血流を改善することでしびれの緩和を目指します。
同時に、肩甲骨や頸椎の動きを改善する施術を行うことで、根本的な原因の改善を目指します。
3.5 鍼灸治療の効果とメカニズム
鍼灸治療は、自然治癒力を高めることで五十肩の症状改善を促します。鍼やお灸の刺激は、自律神経系、内分泌系、免疫系などに作用し、体の機能を調整します。具体的には、次のようなメカニズムで効果を発揮すると考えられています。
効果 | メカニズム |
鎮痛効果 | エンドルフィンなどの鎮痛物質の分泌を促進 |
血行促進効果 | 血管拡張作用により血流を改善 |
筋肉の緊張緩和 | 筋肉の過緊張を抑制し、柔軟性を向上 |
炎症抑制効果 | 炎症物質の産生を抑え、炎症を鎮静 |
これらの効果により、五十肩の痛みやしびれ、関節可動域制限などを改善へと導きます。鍼灸治療は、身体への負担が少ないため、他の治療法と併用することも可能です。
4. 五十肩の痛みを和らげる日常生活の注意点

五十肩の痛みは、日常生活のちょっとした工夫で軽減できることがあります。適切なケアを続けることで、症状の悪化を防ぎ、回復を早める効果も期待できます。ご自身の症状に合った方法を取り入れ、快適な生活を取り戻しましょう。
4.1 睡眠時の姿勢
五十肩の痛みは、夜間や朝方に強くなる傾向があります。これは、睡眠中の姿勢が肩関節に負担をかけていることが原因の一つです。痛みを悪化させないためには、自分に合った寝姿勢を見つけることが重要です。
4.1.1 仰向けで寝る場合
仰向けで寝る場合は、患側の腕の下にタオルやクッションなどを敷き、肩関節への負担を軽減しましょう。腕を軽く外側に開き、リラックスした姿勢を保つことが大切です。抱き枕を使うのも効果的です。
4.1.2 横向きで寝る場合
横向きで寝る場合は、患側を上にして寝ないようにしましょう。健側を下にして、患側の腕を体よりも少し前に出して、軽く曲げた状態で寝ることをお勧めします。この姿勢は、肩関節への圧迫を軽減し、痛みの悪化を防ぎます。
4.2 入浴方法
入浴は、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。五十肩の痛みを軽減するためにも、正しい入浴方法を心がけましょう。
4.2.1 お湯の温度
お湯の温度は、38~40度程度のぬるめのお湯に設定しましょう。熱すぎるお湯は、炎症を悪化させる可能性があります。ゆっくりと時間をかけて入浴することで、全身の血行が促進され、肩の筋肉もリラックスします。
4.2.2 入浴剤
入浴剤を使用する場合は、生薬系や炭酸系の入浴剤がおすすめです。これらの入浴剤は、血行促進効果が高く、肩こりの緩和にも役立ちます。香りにも癒されるので、リラックス効果も期待できます。
4.2.3 湯船につかる時間
湯船につかる時間は、10~20分程度を目安にしましょう。長時間入浴すると、体力を消耗してしまう場合があるので、注意が必要です。入浴後は、体を冷やさないように、すぐに服を着て保温しましょう。
4.3 運動療法とストレッチ
五十肩の痛みが強い急性期は、無理に動かさないことが大切です。痛みが落ち着いてきたら、肩関節の可動域を広げるための運動療法やストレッチを始めましょう。ただし、痛みを感じない範囲で行うことが重要です。無理に動かすと、症状を悪化させる可能性があります。
運動療法・ストレッチ | 方法 | 注意点 |
振り子運動 | 体を前かがみにし、リラックスした状態で腕を振り子のように前後に、左右に、円を描くように動かす。 | 痛みを感じない範囲で、ゆっくりと行う。 |
タオルを使ったストレッチ | タオルの両端を持ち、背中に回し、上下に動かす。 | 無理に伸ばさず、心地よいと感じる範囲で行う。 |
壁を使ったストレッチ | 壁に手をつけ、指を壁に沿って上に動かしていく。 | 肩に痛みを感じたら、無理せず中止する。 |
これらの運動療法やストレッチは、毎日継続して行うことで効果を発揮します。痛みがある場合は、無理せず中止し、専門家に相談しましょう。ストレッチの方法については、動画サイトなどで確認することもできますが、自己流で行うと症状を悪化させる可能性があるので、注意が必要です。
4.4 理学療法、マッサージ
五十肩の症状によっては、理学療法やマッサージが有効な場合があります。理学療法では、専門家による指導のもと、肩関節の可動域 エクササイズや筋力トレーニングなどを行います。マッサージは、肩周辺の筋肉の緊張を和らげ、血行を促進する効果があります。
ただし、強いマッサージは逆効果になる場合もあるので、施術を受ける際は、信頼できる専門家を選ぶことが大切です。
4.5 鍼灸治療のメリット・デメリット
五十肩の治療法として、鍼灸治療を選択する方もいます。鍼灸治療は、肩周辺のツボに鍼やお灸を施すことで、痛みを和らげ、血行を促進する効果が期待できます。以下に、鍼灸治療のメリット・デメリットをまとめました。
メリット | デメリット |
薬を使わないため、副作用が少ない。 | 施術者に技術の差がある場合がある。 |
自然治癒力を高める効果が期待できる。 | 鍼やお灸に抵抗がある人もいる。 |
肩こりや冷え性など、他の症状にも効果がある場合がある。 | 効果には個人差がある。 |
鍼灸治療を受ける際は、経験豊富な鍼灸師に相談し、ご自身の症状に合った治療法を選択することが大切です。また、鍼灸治療の効果には個人差があることを理解しておく必要があります。
5. まとめ

五十肩は、肩関節周囲の炎症や癒着によって引き起こされる痛みや運動制限を特徴とする疾患です。その痛みは、急性期、慢性期、炎症期など、段階によって異なり、夜も眠れないほどの激痛やしびれを伴うこともあります。この記事では、それぞれの痛みの種類に合わせて、鍼灸治療による具体的なアプローチ方法を解説しました。
鍼灸治療は、五十肩の痛みの緩和や可動域改善に効果的です。急性期の激しい痛みには、鎮痛効果のあるツボへの鍼治療が有効です。慢性期の運動制限には、肩関節周囲の筋肉の緊張を緩和する鍼治療や、血行を促進するお灸が有効です。
また、炎症期には、炎症を抑えるツボへの鍼治療が効果的です。五十肩に伴うしびれに対しても、関連する経絡やツボへの鍼治療で症状の改善が期待できます。鍼灸治療は、身体への負担が少ないため、他の治療法と併用することも可能です。
日常生活における注意点と合わせて、鍼灸治療を取り入れることで、五十肩の症状改善を目指しましょう。
五十肩の痛みでお困りの方は、ぜひ当院へご相談ください。
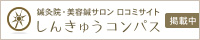




コメント