四十肩と五十肩の違いとは?原因と症状、整体での効果的な対処方法を徹底解説!
- 鍼灸院 横浜文庫
- 3月6日
- 読了時間: 15分

四十肩と五十肩、どちらも肩の痛みと可動域制限に悩まされる症状ですが、一体何が違うのでしょうか? 実は呼び方が違うだけで、根本的には同じ病態を指します。この違いに戸惑う方も多いのではないでしょうか。さらに、効果的な対処法も気になるところです。
この記事では、四十肩と五十肩の違いを分かりやすく解説し、その原因や症状、そして整体における効果的な対処方法を詳しくご紹介します。四十肩・五十肩の痛みやつらさから解放され、快適な日常生活を取り戻すためのヒントが満載です。
肩の痛みを我慢せず、適切なケアで健康な毎日を送りましょう。
1. 四十肩と五十肩の違い

「四十肩」「五十肩」という言葉をよく耳にしますが、この2つには一体どんな違いがあるのでしょうか。実は、医学的にはどちらも同じ病態を指しており、正式名称は「肩関節周囲炎」といいます。違いは、主に発症年齢にあります。
1.1 四十肩とは
四十肩とは、40歳前後で発症する肩関節周囲炎のことを指します。文字通り、40歳前後の方に多く見られる症状ですが、30代後半から50代前半で発症することもあります。肩の痛みや可動域制限が主な症状です。
1.2 五十肩とは
五十肩とは、50歳前後で発症する肩関節周囲炎のことを指します。こちらも文字通り、50歳前後の方に多く見られる症状ですが、40代後半から60代前半で発症することもあります。四十肩と同様に、肩の痛みや可動域制限が主な症状です。
1.3 呼び方の違いだけで病態は同じ
医学的には、四十肩と五十肩はどちらも「肩関節周囲炎」という同じ病態を指します。つまり、呼び方が違うだけで、根本的な原因や症状に違いはありません。肩関節周囲の筋肉や腱、靭帯などの組織に炎症が起こり、痛みや動かしにくさを引き起こします。
| 四十肩 | 五十肩 |
正式名称 | 肩関節周囲炎 | |
発症年齢 | 40歳前後 | 50歳前後 |
主な症状 | 肩の痛み、可動域制限 |
1.4 発症年齢による違い
四十肩と五十肩の唯一の違いは、発症年齢です。四十肩は40歳前後、五十肩は50歳前後で発症することが多いですが、あくまで目安であり、個人差があります。30代で五十肩のような症状が出る場合もあれば、60代で四十肩のような症状が出る場合もあります。年齢だけで判断せず、肩に痛みや違和感を感じたら、早めに整体院に相談することをおすすめします。
加齢とともに肩関節周囲の組織が衰えやすくなるため、年齢を重ねるごとに発症リスクは高まります。しかし、適切なケアを行うことで、症状の進行を抑制し、早期回復を目指すことができます。
2. 四十肩・五十肩の原因

四十肩・五十肩は、肩関節周囲の組織の炎症や痛み、可動域制限を特徴とする疾患ですが、その原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていると考えられています。加齢に伴う変化や生活習慣、そして外傷なども原因として挙げられます。以下に、四十肩・五十肩の主な原因を詳しく解説します。
2.1 加齢による変化
加齢に伴い、肩関節周囲の組織は徐々に変化していきます。腱や靭帯、関節包などの組織は弾力性を失い、柔軟性が低下します。また、筋肉も衰え、肩関節の安定性が損なわれやすくなります。こうした加齢による変化は、四十肩・五十肩の発症リスクを高める大きな要因となります。
特に、40代以降は肩関節周囲の組織の老化が顕著になるため、四十肩・五十肩の発症率が高くなると言われています。50代に発症するから「五十肩」と呼ばれる所以でもあります。
2.2 肩関節周囲の組織の炎症
肩関節周囲の組織、特に腱板や滑液包などに炎症が生じると、痛みや可動域制限といった四十肩・五十肩の症状が現れます。炎症の原因としては、使い過ぎや繰り返しの動作による負担、肩への外傷、血行不良などが考えられます。炎症が慢性化すると、組織の癒着や拘縮が起こり、症状がさらに悪化することもあります。
腱板炎や滑液包炎などは、四十肩・五十肩と密接な関係があるとされています。
2.3 血行不良
肩関節周囲の血行不良は、組織の修復を遅らせ、炎症を長引かせる原因となります。血行不良は、冷え性や運動不足、長時間のデスクワークなどによって引き起こされます。また、ストレスや睡眠不足も血行不良を招く要因となります。
特に、肩や首周りの筋肉が緊張すると、血管が圧迫され、血行不良が悪化しやすくなります。
2.4 運動不足
運動不足は、肩関節周囲の筋肉を弱らせ、関節の安定性を低下させます。また、血行不良も引き起こし、四十肩・五十肩の発症リスクを高めます。特に、普段から肩をあまり動かさない人は、肩関節周囲の筋肉が硬くなりやすく、炎症を起こしやすくなります。
適度な運動は、肩関節周囲の筋肉を強化し、血行を促進するため、四十肩・五十肩の予防に効果的です。
2.5 姿勢の悪さ
猫背や巻き肩などの姿勢の悪さは、肩関節に負担をかけ、四十肩・五十肩の原因となることがあります。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などで姿勢が悪くなりがちな方は注意が必要です。正しい姿勢を保つことで、肩関節への負担を軽減し、四十肩・五十肩の予防に繋がります。
猫背は肩甲骨の位置がずれる原因となり、肩関節の動きを阻害し、四十肩・五十肩の悪化要因となる可能性があります。
2.6 外傷
転倒やスポーツなどによる肩への外傷は、四十肩・五十肩の直接的な原因となることがあります。強い衝撃によって肩関節周囲の組織が損傷を受けると、炎症や痛みが発生し、可動域制限が生じることがあります。また、過去に受けた肩のケガが、後々四十肩・五十肩を引き起こす原因となる場合もあります。
骨折や脱臼などの大きなケガだけでなく、軽微な打撲なども四十肩・五十肩のきっかけとなることがあります。
原因 | 詳細 |
加齢による変化 | 腱や靭帯、関節包などの組織の弾力性低下、筋肉の衰え |
肩関節周囲の組織の炎症 | 腱板炎、滑液包炎など |
血行不良 | 冷え性、運動不足、長時間のデスクワーク、ストレス、睡眠不足 |
運動不足 | 肩関節周囲の筋肉の弱化、関節の安定性低下、血行不良 |
姿勢の悪さ | 猫背、巻き肩などによる肩関節への負担増加 |
外傷 | 転倒、スポーツなどによる肩への衝撃、過去のケガ |
3. 四十肩・五十肩の症状

四十肩・五十肩は、肩関節周囲の炎症や組織の変性などが原因で、様々な症状が現れます。症状の進行度合いは人それぞれですが、大きく分けて急性期、慢性期、回復期に分けられます。それぞれの時期の特徴的な症状を理解し、適切な対処をすることが重要です。
3.1 肩の痛み
四十肩・五十肩の代表的な症状が肩の痛みです。痛みの程度や性質は時期によって変化します。
3.1.1 急性期
急性期には、鋭い激痛 が走ることがあります。特に夜間や安静時に痛みが強くなる傾向があり、寝返りを打つのも困難になることがあります。また、腕を特定の方向に動かすと、電気が走るような痛みを感じることもあります。炎症が強い時期なので、肩に触れるだけでも痛みを感じることがあります。
3.1.2 慢性期
慢性期に入ると、鋭い痛みは軽減し、鈍い痛み が持続するようになります。肩を動かすと痛みが増しますが、安静時には比較的楽になります。肩のこわばりも強く感じ、動かしにくさが目立つようになります。
3.2 肩の可動域制限
肩の痛みとともに、肩関節の動きが悪くなる可動域制限 も四十肩・五十肩の主な症状です。日常生活に大きな支障をきたすこともあります。
3.2.1 腕が上がらない
腕を真上に上げる動作が困難になります。洗濯物を干したり、高いところの物を取ったりする際に苦労します。また、髪を洗う、顔を洗うといった動作も難しくなります。洋服を着替えることも一苦労です。特に、ブラジャーのホックを後ろで留める、帯を結ぶといった動作は困難になります。
3.2.2 後ろに手が回らない
腕を後ろに回す動作も制限されます。背中を掻いたり、ズボンの後ろポケットに手を入れたりする動作が難しくなります。車の運転でバックミラーを確認する際にも支障が出ることがあります。また、エプロンの紐を後ろで結ぶといった日常動作にも影響が出ます。
3.3 日常生活への影響
四十肩・五十肩の症状は、日常生活の様々な場面で支障をきたします。症状が重くなると、簡単な動作も困難になり、生活の質が低下する可能性があります。
動作 | 具体的な支障 |
着替え | シャツを着たり脱いだりする、ブラジャーのホックを留める、帯を結ぶといった動作が困難になる。 |
髪を洗う | 腕を上げて洗髪することが困難になる。 |
睡眠 | 夜間の痛みで目が覚める、寝返りが打ちにくい。 |
運転 | ハンドル操作やバックミラーの確認が困難になる。 |
仕事 | パソコン作業や書類整理、重い物を持ち上げるといった動作に支障が出る。 |
家事 | 洗濯物を干す、掃除機をかける、料理をするといった動作が困難になる。 |
趣味 | スポーツ、楽器演奏、ガーデニングなど、肩を使う趣味が楽しめなくなる。 |
これらの症状は、日常生活に大きな影響を与える可能性があります。早期に適切な対処 を行うことで、症状の悪化を防ぎ、日常生活への支障を最小限に抑えることが重要です。
4. 四十肩・五十肩の整体での対処方法

四十肩・五十肩の痛みや可動域制限に悩まされている方は、整体での施術が効果的な場合があります。整体では、肩関節周囲の筋肉や組織の状態を丁寧に評価し、個々の状態に合わせた施術プランを立てます。
4.1 整体における四十肩・五十肩へのアプローチ
整体では、四十肩・五十肩の根本原因に対処することを目指します。肩関節だけでなく、周囲の筋肉、靭帯、関節包、神経など、関連する部位全体を考慮した包括的なアプローチが重要です。
痛みや炎症の軽減、可動域の改善、再発予防を目的とした施術を行います。
4.2 四十肩・五十肩に効果的な整体施術
四十肩・五十肩に対して、整体では様々な施術法が用いられます。代表的な施術を以下に紹介します。
4.2.1 マッサージ
肩や首、背中などの筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、痛みや炎症を軽減します。肩甲骨周囲の筋肉を重点的にほぐすことで、肩関節の動きをスムーズにします。肩甲骨はがしと呼ばれる施術も効果的です。硬くなった筋肉を丁寧に解きほぐすことで、肩の可動域を広げます。
4.2.2 ストレッチ
肩関節周囲の筋肉や靭帯の柔軟性を高めることで、可動域制限を改善します。一人で行うストレッチでは届かない肩甲骨の間や、肩関節の奥深くにある筋肉までアプローチできます。四十肩・五十肩で硬くなりやすい筋肉を重点的にストレッチすることで、痛みの緩和と可動域の改善を促します。
4.2.3 関節モビライゼーション
肩関節の動きを滑らかにし、可動域を拡大させるテクニックです。関節に適切な刺激を与えることで、関節の動きを正常化させます。熟練した施術者によって行われることで、安全かつ効果的に関節の機能を回復させます。
4.2.4 姿勢矯正
不良姿勢は、肩関節への負担を増大させ、四十肩・五十肩の悪化要因となります。猫背や巻き肩などの姿勢の歪みを矯正することで、肩関節への負担を軽減し、再発予防に繋がります。姿勢改善のためのエクササイズ指導も行います。
施術法 | 効果 | 対象 |
マッサージ | 筋肉の緊張緩和、血行促進、痛み軽減 | 肩こり、筋肉の硬直が強い方 |
ストレッチ | 柔軟性向上、可動域制限改善 | 関節の動きが悪くなっている方 |
関節モビライゼーション | 関節の動きを滑らかにする、可動域拡大 | 関節の可動制限が強い方 |
姿勢矯正 | 姿勢改善、肩関節への負担軽減 | 猫背、巻き肩、姿勢が悪い方 |
これらの施術は単独で行うだけでなく、組み合わせて行うことでより効果的です。整体師は、個々の症状や状態に合わせて最適な施術プランを提案します。
5. 整体以外の対処方法

四十肩・五十肩の痛みや可動域制限を改善するには、整体以外にも様々な対処法があります。症状や生活スタイルに合わせて、最適な方法を選びましょう。
5.1 医療機関での治療
医療機関では、四十肩・五十肩の症状に合わせて、様々な治療法が提供されます。痛みが強い場合や、なかなか症状が改善しない場合は、医療機関への受診を検討しましょう。
5.1.1 薬物療法
痛みや炎症を抑えるために、消炎鎮痛剤や湿布などが処方されることがあります。市販薬を使用する場合は、用法・用量を守り、適切に使用しましょう。
5.1.2 注射療法
炎症や痛みを抑えるために、ステロイド注射やヒアルロン酸注射などが行われることがあります。注射療法は、痛みの軽減に効果的ですが、効果の持続期間には個人差があります。
5.1.3 理学療法
肩関節の可動域を広げたり、筋力をつけるための運動療法が行われます。理学療法士の指導のもと、適切な運動を行うことで、症状の改善を図ることができます。
5.2 自宅でできるケア
自宅でも、痛みを和らげたり、肩関節の動きを改善するためのケアを行うことができます。継続して行うことが大切です。
5.2.1 温熱療法
温めることで、血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。蒸しタオルや温熱パッド、入浴などで肩を温めましょう。温める時間は10~15分程度を目安とし、低温やけどに注意しましょう。
5.2.2 ストレッチ
肩関節の可動域を広げるためのストレッチは、痛みが出ない範囲で行いましょう。無理に動かすと症状が悪化することがあるので、痛みを感じたらすぐに中止してください。
ストレッチの種類 | 方法 | 注意点 |
振り子運動 | 体を前かがみにし、腕をだらりと下げて、前後に小さく振る。 | 痛みが出ない範囲で行う。 |
タオルストレッチ | タオルの両端を持ち、背中に回して上下に動かす。 | 無理に伸ばさない。 |
壁押しつけストレッチ | 壁に手をついて、体を壁に近づけるようにする。 | 痛みが出ない範囲で行う。 |
5.2.3 痛み止め
市販の鎮痛剤を使用することで、痛みを一時的に和らげることができます。用法・用量を守って使用し、痛みが続く場合は医療機関を受診しましょう。 ロキソニンSやバファリンなどの市販薬が利用できます。薬剤師に相談して適切な薬を選ぶようにしましょう。
これらの方法を組み合わせて行うことで、四十肩・五十肩の症状改善を効果的にサポートできます。自分の症状に合った方法を選び、継続して行うことが大切です。
6. 四十肩・五十肩の予防法

四十肩・五十肩は、つらい症状が出る前に、予防に取り組むことが大切です。日々の生活習慣を少し見直すだけで、発症リスクを減らすことができます。ここでは、効果的な予防法をいくつかご紹介します。
6.1 適度な運動
肩関節周囲の筋肉を鍛え、柔軟性を保つことは、四十肩・五十肩の予防に効果的です。激しい運動は必要ありません。日常生活の中で無理なく続けられる運動を選びましょう。
6.1.1 ウォーキング
ウォーキングは、手軽に始められる全身運動です。適度な強度で、30分程度を目安に行うと良いでしょう。肩甲骨を意識的に動かすことで、肩関節周囲の筋肉も効果的に鍛えられます。
6.1.2 水泳
水泳は、浮力によって関節への負担が少ないため、肩に痛みがある方にもおすすめの運動です。特にクロールや背泳ぎは、肩甲骨の動きが大きく、四十肩・五十肩の予防に効果的です。
6.1.3 ラジオ体操
ラジオ体操は、全身の筋肉をバランスよく動かせるため、肩関節周囲の筋肉の強化にも役立ちます。毎日続けることで、柔軟性を維持し、四十肩・五十肩の予防につながります。
6.2 ストレッチ
肩関節周囲の筋肉の柔軟性を保つことは、四十肩・五十肩の予防に非常に重要です。下記のストレッチは、肩甲骨の動きを意識しながら、ゆっくりと行いましょう。痛みを感じたら無理せず中止してください。
6.2.1 肩甲骨回し
両腕を肩の高さまで上げて、肘を曲げ、前後に大きく回します。肩甲骨を意識的に動かすことで、肩関節周囲の筋肉の柔軟性を高めます。
6.2.2 腕の振り子運動
軽く前かがみになり、リラックスした状態で腕を振り子のように前後に、左右に振ります。肩関節周囲の筋肉をほぐし、血行を促進する効果があります。
6.2.3 タオルストレッチ
タオルの両端を持ち、頭の上を通して、背中にタオルを回します。無理のない範囲で、タオルを上下に動かし、肩関節の可動域を広げます。痛みが強い場合は、無理に行わないようにしましょう。
6.3 姿勢改善
猫背などの悪い姿勢は、肩関節周囲の筋肉に負担をかけ、四十肩・五十肩のリスクを高めます。日頃から正しい姿勢を意識することで、予防効果が期待できます。
6.3.1 正しい姿勢のポイント
ポイント | 説明 |
頭の位置 | 耳の穴と肩の先端が一直線になるように意識します。 |
背筋 | 背筋を伸ばし、胸を張ります。 |
肩甲骨 | 肩甲骨を寄せるように意識します。 |
骨盤 | 骨盤を立て、背骨のS字カーブを保ちます。 |
デスクワーク中は、こまめに休憩を取り、軽いストレッチを行うなど、身体を動かすことを心がけましょう。
6.4 冷え対策
冷えは、血行不良を招き、肩関節周囲の筋肉を硬くしてしまいます。特に冬場は、身体を冷やさないように注意が必要です。
6.4.1 保温
寒い時期は、マフラーやストールなどで首元を温め、肩や背中を冷やさないようにしましょう。
6.4.2 入浴
湯船にゆっくりと浸かり、身体を温めることで、血行が促進され、肩関節周囲の筋肉の緊張が和らぎます。38~40度くらいのぬるめのお湯に、15~20分程度浸かるのがおすすめです。入浴剤を使用するのも良いでしょう。
7. まとめ

四十肩・五十肩は、肩関節周囲の炎症や血行不良、加齢などが原因で発症する、肩の痛みや可動域制限を伴う症状です。四十肩と五十肩は呼び方が違うだけで、基本的には同じ病態を指します。
違いは主に発症年齢であり、40代で発症すれば四十肩、50代で発症すれば五十50呼ばれます。症状は急性期と慢性期に分かれ、急性期には激しい痛みが、慢性期には痛みが軽減する一方、可動域制限が顕著になります。これらの症状は日常生活にも大きな影響を与え、着替えや髪を洗うといった動作が困難になることもあります。
整体では、マッサージやストレッチ、関節モビライゼーション、姿勢矯正などを通して、肩関節周囲の筋肉の緊張を緩和し、血行を促進することで、痛みや可動域制限の改善を目指します。整体以外の対処法としては、医療機関での治療や、自宅でできる温熱療法、ストレッチ、市販の痛み止めなどがあります。また、予防には適度な運動、ストレッチ、正しい姿勢の維持、冷え対策などが有効です。
四十肩・五十肩の症状でお悩みの方は、我慢せずに整体院や医療機関に相談し、適切な対処をするようにしましょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
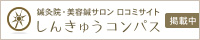




コメント