【鍼灸師が解説】五十肩になりやすい人の特徴|症状悪化を防ぐ注意点と効果的な治療法
- 鍼灸院 横浜文庫
- 3月21日
- 読了時間: 12分

四十肩・五十肩の痛みやしびれに悩まされていませんか?
日常生活に支障をきたすほど辛い五十肩ですが、適切なケアと治療によって改善が期待できます。
この記事では、五十肩になりやすい人の特徴を詳しく解説。年齢や性別、生活習慣など、様々な要因からあなたのリスクをチェックできます。
また、症状を悪化させないための注意点や、効果的な治療法についてもご紹介します。
肩の痛みを我慢せず、快適な毎日を取り戻すために、ぜひこの記事を参考にしてみてください。鍼灸治療が五十肩に効果的な理由や作用機序についても解説しているので、治療院選びのヒントにもなるでしょう。
1. 五十肩とはどんな病気?

五十肩は、正式には肩関節周囲炎と呼ばれ、肩関節とその周囲の組織に炎症や痛み、運動制限が生じる病気です。
40歳代から50歳代に多く発症することから、五十肩という俗称で広く知られています。
肩関節の動きが悪くなり、日常生活に支障をきたすこともあります。夜間痛が強く、睡眠不足に悩まされる方も少なくありません。
1.1 五十肩の症状
五十肩の症状は、炎症の進行度合いによって大きく3つの時期に分けられます。
時期 | 症状 | 期間 |
急性期(炎症期) | 強い痛みが特徴で、特に夜間や安静時にも痛みが強く現れます。肩を動かすと激痛が走り、少し動かすだけでも困難になります。 | 数週間~数か月 |
慢性期(拘縮期) | 痛みはやや軽減しますが、肩関節の動きが制限され、腕が上がらなかったり、背中に手が回らなかったりといった症状が現れます。日常生活動作に支障をきたすことが多くなります。 | 数か月~半年 |
回復期(回復期) | 痛みと動きの制限が徐々に改善していきます。時間をかけて自然に回復していくことが多いですが、完全に元の状態に戻るまでには1年以上かかる場合もあります。 | 数か月~数年 |
これらの時期は明確に区別されるものではなく、症状の経過には個人差があります。
1.2 五十肩の原因
五十肩の明確な原因は未だ解明されていませんが、加齢に伴う肩関節周囲の組織の変性や、肩関節の使い過ぎ、血行不良、外傷などが発症に関与していると考えられています。肩関節周囲の筋肉や腱、靭帯、関節包などが炎症を起こし、線維化することで痛みが生じ、関節の動きが悪くなります。
また、糖尿病、高血圧、高脂血症などの生活習慣病との関連も指摘されています。これらの病気は、血管の老化を促進し、血行不良を引き起こすため、五十肩の発症リスクを高める可能性があります。精神的なストレスや、猫背などの姿勢の悪さも、肩関節への負担を増大させ、五十肩の発症を促す要因となることがあります。
2. 五十肩になりやすい人の特徴

五十肩は誰にでも起こりうる疾患ですが、特に以下の特徴に当てはまる方は注意が必要です。これらの特徴を理解することで、五十肩の予防や早期発見に役立てましょう。
2.1 40代~50代の人
五十肩は、その名の通り40代~50代に多く発症します。加齢に伴い、肩関節周囲の組織の柔軟性が低下し、炎症や痛みを起こしやすくなるためです。40代に発症した場合は四十肩、50代に発症した場合は五十肩と呼びますが、医学的にはどちらも同じ「肩関節周囲炎」です。
2.2 女性
五十肩は、男性よりも女性に多く発症する傾向があります。女性ホルモンの変動や、男性に比べて筋肉量が少ないことなどが影響していると考えられています。閉経後の女性は特に注意が必要です。
2.3 糖尿病、高血圧、高脂血症などの持持病がある人
糖尿病、高血圧、高脂血症などの生活習慣病は、血管の老化を促進し、肩関節周囲の組織への血流を阻害する可能性があります。これらの持病がある方は、五十肩のリスクが高まるだけでなく、症状が重症化しやすいため、注意が必要です。
2.4 猫背や姿勢が悪い人
猫背や姿勢が悪いと、肩甲骨の動きが制限され、肩関節周囲の筋肉や腱に負担がかかりやすくなります。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などで姿勢が悪くなりがちな方は、意識的に姿勢を正すように心がけましょう。
2.5 肩を酷使する人
野球やテニス、バレーボールなどのスポーツ選手や、重い荷物を運ぶ作業をする人など、肩を酷使する人は、肩関節周囲の組織に炎症を起こしやすく、五十肩になりやすい傾向があります。適切な休息やストレッチを行うことで、肩への負担を軽減することが重要です。
2.6 精神的なストレスを抱えている人
ストレスは、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高める原因となります。肩周りの筋肉が緊張すると、血行が悪くなり、肩関節の動きが悪くなって五十肩を引き起こしやすくなります。ストレスをため込まないよう、リラックスする時間を作る、趣味に没頭するなど、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。
2.7 甲状腺の機能低下がある人
甲状腺ホルモンは、体の代謝を調節する重要なホルモンです。甲状腺の機能が低下すると、代謝が低下し、肩関節周囲の組織の修復が遅れ、五十肩になりやすくなると言われています。甲状腺機能低下症の症状(倦怠感、体重増加、便秘など)がある場合は、医療機関への受診をおすすめします。
2.8 更年期障害の症状がある人
更年期障害は、女性ホルモンの減少によって起こる様々な症状です。更年期障害の症状の一つとして、肩こりや関節痛などが挙げられます。これらの症状は五十肩と似ているため、自己判断せずに、専門家への相談をおすすめします。
日常生活での注意点 | 詳細 |
パソコン作業時の姿勢 | 長時間のパソコン作業は、猫背になりやすく、肩関節への負担を増大させます。こまめな休憩を挟み、ストレッチを行う、正しい姿勢を保つための工夫をするなど、肩への負担を軽減することが重要です。 |
スマートフォンの使用 | スマートフォンの長時間使用は、下を向いた姿勢になりやすく、首や肩への負担が大きくなります。使用する際は、画面を目の高さに持ってくる、肘を支えるなど、姿勢に気を付けましょう。 |
バッグの持ち方 | いつも同じ肩に重いバッグをかけていると、肩への負担が偏り、五十肩のリスクを高めます。リュックサックを使用する、左右の肩で交互に持つなど、負担を分散させるようにしましょう。 |
睡眠時の姿勢 | うつ伏せで寝る際は、肩関節が内側にねじれた状態になり、負担がかかりやすくなります。横向きまたは仰向けで寝るように心がけましょう。抱き枕を使うのも効果的です。 |
3. 五十肩の注意点|症状を悪化させないために

五十肩の痛みやは、日常生活に大きな支障をきたします。適切なケアを怠ると、症状が悪化し、回復が遅れる可能性があります。五十肩の症状を悪化させないための注意点について、詳しく解説します。
3.1 無理に動かさない
痛みがあるからといって、肩を全く動かさないのは逆効果です。しかし、痛みを我慢して無理に動かすと、炎症が悪化し、痛みが強くなることがあります。肩の可動域が狭くなっている場合は、無理に動かそうとせず、痛みのない範囲で優しく動かすようにしましょう。
3.2 冷やさない
冷えは血行不良を招き、肩の筋肉や関節を硬くするため、五十肩の症状を悪化させる可能性があります。特に冬場は、肩を冷やさないように注意が必要です。暖かい服装を心がけ、入浴で体を温めるのも効果的です。また、就寝時は肩が冷えないように、タオルケットなどをかけて寝るようにしましょう。痛みがある場合は、保冷剤ではなく温湿布を使用するのも良いでしょう。
3.3 同じ姿勢を長時間続けない
デスクワークやパソコン作業など、同じ姿勢を長時間続けると、肩周りの筋肉が緊張し、血行が悪くなるため、五十肩の症状を悪化させる可能性があります。1時間ごとに軽いストレッチや体操を行い、肩周りの筋肉をほぐすようにしましょう。また、正しい姿勢を保つことも大切です。
3.4 適切な運動を行う
五十肩の痛みが強い時期は、無理に運動をするのは避けましょう。痛みが落ち着いてきたら、医師や理学療法士の指導のもと、肩関節の可動域を広げるための運動療法を行うことが重要です。ストレッチや筋力トレーニング、体操など、自分に合った運動を行い、肩周りの筋肉を強化し、柔軟性を高めることで、再発予防にも繋がります。具体的な運動方法については、後述の理学療法の項目で詳しく解説します。
3.5 専門家への相談
五十肩の症状が長引く場合や、痛みが強い場合は、自己判断で対処せずに、専門家(鍼灸師など)に相談しましょう。適切な診断と治療を受けることで、症状の悪化を防ぎ、早期回復を目指せます。 以下の表に、五十肩で専門家に相談する目安をまとめました。当てはまる項目が多いほど、早めに相談することが推奨されます。
症状 | 説明 |
夜間痛がひどい | 夜寝ている時に痛みで目が覚める、痛みで寝付けないなど、日常生活に支障が出ている場合。 |
痛みが1ヶ月以上続く | 適切なケアを行っても、痛みが改善しない場合。 |
腕が上がらない、後ろに回らない | 日常生活動作(服を着る、髪を洗うなど)に支障が出ている場合。 |
肩だけでなく、腕や手にも痛みやしびれがある | 他の疾患の可能性もあるため、注意が必要です。 |
発熱を伴う | 感染症などの他の疾患の可能性もあるため、注意が必要です。 |
4. 五十肩の治療法

五十肩の治療は、大きく分けて保存療法と手術療法の2種類があります。ほとんどの五十肩は保存療法で改善しますが、痛みが強い場合や日常生活に支障が出る場合は、手術療法が選択されることもあります。
4.1 保存療法
保存療法は、手術を行わずに痛みや炎症を抑え、肩関節の動きを改善することを目的とした治療法です。具体的には、以下のような方法があります。
4.1.1 薬物療法
痛みや炎症を抑えるために、鎮痛剤や消炎鎮痛剤などの内服薬、湿布などの外用薬が使用されます。痛みが強い時期には、これらの薬剤で症状を緩和することが重要です。
4.1.2 注射
炎症や痛みを抑えるために、肩関節内にステロイド注射やヒアルロン酸注射を行うことがあります。ステロイド注射は強力な抗炎症作用がありますが、繰り返し行うと副作用のリスクがあるため、使用頻度には注意が必要です。ヒアルロン酸注射は、関節の動きを滑らかにする効果が期待できます。
4.1.3 理学療法
肩関節の動きを改善し、周囲の筋肉を強化するための運動療法や物理療法を行います。理学療法士の指導のもと、自分に合った運動プログラムを作成し、継続して行うことが大切です。温熱療法や電気刺激療法なども併用されることがあります。
種類 | 内容 | 効果 |
運動療法 | ストレッチ、筋力トレーニング、関節可動域訓練など | 肩関節の柔軟性や筋力を向上させることで、痛みの軽減や関節の動きを改善する |
物理療法 | 温熱療法、電気刺激療法、超音波療法など | 痛みや炎症を軽減し、組織の修復を促進する |
4.2 手術療法
保存療法で効果が得られない場合や、関節が拘縮して動かなくなってしまった場合などには、手術療法が検討されます。手術には、関節鏡手術や人工関節置換術などがあります。手術療法は最終手段であり、医師とよく相談した上で決定する必要があります。
種類 | 内容 | 適応 |
関節鏡手術 | 関節内に小さなカメラを挿入し、癒着した組織を切除したり、関節内の炎症を抑える処置を行う | 保存療法で効果が得られない場合、関節内に癒着がある場合 |
人工関節置換術 | 損傷した関節を人工関節に置き換える | 関節の変形が進行している場合、他の治療法で効果が得られない場合 |
5. 鍼灸治療で五十肩を改善

五十肩でお悩みの方にとって、鍼灸治療は効果的な選択肢の一つです。肩の痛みや動きの制限といった五十肩の症状に、鍼灸治療はどのようにアプローチするのでしょうか。その効果や作用機序について詳しく解説します。
5.1 鍼灸治療の効果
鍼灸治療は、肩関節周囲の筋肉の緊張を緩和し、血行を促進することで、五十肩の症状改善に効果を発揮します。具体的には、次のような効果が期待できます。
効果 | 詳細 |
疼痛の緩和 | 肩の痛みや腕を動かした時の痛みを軽減します。 |
可動域の改善 | 腕を上げる、回すといった動作がしやすくなります。 |
炎症の抑制 | 肩関節の炎症を抑え、症状の悪化を防ぎます。 |
血行促進 | 肩関節周囲の血行を良くし、筋肉や組織の修復を促します。 |
自律神経の調整 | ストレスなどによる自律神経の乱れを整え、症状の改善をサポートします。 |
これらの効果により、日常生活での動作がスムーズになり、痛みや不快感から解放されることが期待できます。
5.2 五十肩への鍼灸治療の作用機序
鍼灸治療が五十肩に効果を発揮するメカニズムは、主に以下の3つの作用によるものと考えられています。
5.2.1 1. ゲートコントロールセオリー
鍼刺激によって、痛み以外の感覚情報が神経を伝わることで、痛みの信号が脳に伝達されるのを抑制する作用です。これは、痛みを和らげる即効性の効果に繋がります。
5.2.2 2. 末梢神経への作用
鍼を刺すことで、局所の血流が改善され、筋肉の緊張が緩和されます。また、痛みや炎症を引き起こす物質の産生が抑制されることで、肩の痛みや動きの制限が改善されます。
5.2.3 3. ホルモン分泌への作用
鍼灸刺激は、脳内においてエンドルフィンなどの鎮痛作用を持つホルモンの分泌を促進します。エンドルフィンは、モルヒネの数倍もの鎮痛効果を持つと言われており、自然治癒力を高める効果も期待できます。 また、セロトニンの分泌も促進され、精神的なストレスの緩和にも繋がります。
これらの作用が複合的に働くことで、五十肩の症状を根本的に改善していくと考えられています。五十肩の症状でお悩みの方は、鍼灸治療を試してみる価値があるでしょう。ご自身の症状に合った適切な治療を受けるために、鍼灸師とよく相談することが大切です。
6. まとめ

この記事では、五十肩になりやすい人の特徴、症状悪化を防ぐ注意点、そして効果的な治療法について解説しました。
五十肩は40代~50代の女性に多く、糖尿病などの持病、猫背、肩の酷使、ストレスなども発症リスクを高めます。症状を悪化させないためには、無理に肩を動かしたり、冷やしたりせず、同じ姿勢を長時間続けないことが重要です。適切な運動も効果的ですが、痛みが強い場合は専門家への相談が必要です。
五十肩の治療法には、薬物療法、注射、理学療法などの保存療法と、手術療法があります。保存療法で効果が不十分な場合、手術が検討されます。また、鍼灸治療は、肩周囲の筋肉の緊張を緩和し、血行を改善することで、痛みや可動域制限の改善に効果が期待できます。鍼灸治療は、五十肩の症状緩和に有効な選択肢の一つと言えるでしょう。
日常生活における注意点を守り、適切な治療を受けることで、五十肩の早期改善を目指しましょう。お困りの際は、当院へご相談ください。
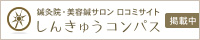




コメント