五十肩の筋トレ方法|鍼灸との併用で効果アップ!自宅でできる簡単ストレッチ
- 鍼灸院 横浜文庫
- 5月20日
- 読了時間: 8分

五十肩で悩んでいませんか?
肩の痛みや動かしにくさは日常生活に大きな支障をきたしますよね。このページでは、五十肩の症状や原因、そして自宅でできる効果的な筋トレ方法とストレッチを詳しく解説します。
五十肩の痛みがある急性期から、痛みが落ち着いてきた慢性期まで、それぞれの時期に適した運動方法を紹介するので、ご自身の状態に合わせて実践できます。
さらに、五十肩への効果が期待される鍼灸との併用によるメリットについても分かりやすく説明します。
このページを読めば、五十肩の改善に必要な知識と具体的な方法が理解でき、痛みや動かしにくさから解放されるための第一歩を踏み出せるはずです。辛い五十肩を克服し、快適な日常生活を取り戻しましょう。
1. 五十肩とは?

五十肩とは、正式には肩関節周囲炎と呼ばれる、肩関節の痛みと運動制限を特徴とする疾患です。40代から50代に多く発症することから、五十肩と呼ばれていますが、実際には30代や60代以降に発症することもあります。加齢とともに肩関節の周りの組織が炎症を起こしたり、癒着したりすることで、肩の痛みや動かしにくさが生じます。
1.1 五十肩の症状
五十肩の症状は、大きく分けて痛みと運動制限の2つがあります。痛みの程度や種類、運動制限の範囲は個人差が大きく、症状の出方も人それぞれです。
夜間に痛みが強くなる夜間痛に悩まされる方も多くいらっしゃいます。
主な症状を以下にまとめました。
症状 | 詳細 |
痛み | 安静時痛、運動時痛、夜間痛など。肩だけでなく、腕や背中、首にまで広がることもあります。 |
運動制限 | 腕を上げること、後ろに回すこと、外側に捻ることなどが困難になります。日常生活動作にも支障をきたすことがあります。着替えや髪を洗う、高いところの物を取るといった動作が難しくなることもあります。 |
関節の硬さ | 肩関節の動きが悪くなり、スムーズに動かせなくなります。 |
腫れ | 炎症により肩関節が腫れることがあります。 |
熱感 | 炎症により肩関節に熱感を感じることがあります。 |
1.2 五十肩の原因
五十肩の明確な原因は未だ解明されていませんが、加齢による肩関節周囲の組織の変性、肩の使い過ぎ、怪我、糖尿病、甲状腺疾患などが発症の誘因として考えられています。
また、肩関節の周りの筋肉や腱、靭帯などの組織が炎症を起こしたり、癒着することで痛みや運動制限が生じるとされています。
特に、肩甲骨の動きが悪くなると、肩関節に負担がかかりやすく、五十肩のリスクを高めると言われています。
1.3 五十肩になりやすい人の特徴
五十肩になりやすい人の特徴としては、40代~50代であること、デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けることが多い人、猫背気味の人、運動不足の人、などが挙げられます。また、女性は男性よりも発症しやすい傾向にあります。更年期障害の症状の一つとして現れる場合もあるため、注意が必要です。
ストレスや睡眠不足なども、五十肩の発症リスクを高める要因と考えられています。日常生活で肩に負担をかけないように意識し、適度な運動を心がけることが大切です。
2. 五十肩の筋トレ方法

五十肩の筋トレは、症状の時期に合わせて適切な方法で行うことが重要です。痛みがある急性期と、痛みが落ち着いてきた慢性期で、それぞれ適切な筋トレ方法が異なります。
2.1 急性期(痛みがある時期)の筋トレ方法
急性期は、激しい痛みがある時期です。この時期は、無理に動かすと炎症が悪化し、痛みがさらに強くなる可能性があります。そのため、激しい運動は避け、痛みの出ない範囲で優しく動かすことを意識しましょう。
2.1.1 痛みを悪化させないための注意点
● 痛みを感じたらすぐに運動を中止する
● 反動をつけずにゆっくりと動かす
● 呼吸を止めずに自然な呼吸を続ける
● 入浴後など体が温まっている時に行う
急性期におすすめの筋トレとしては、以下のものがあります。
筋トレ | 方法 | 回数 |
振り子運動 | 体を前かがみにし、リラックスした状態で腕を振り子のように前後に、左右に、円を描くように振る | 10回ずつ |
肩甲骨体操 | 肩甲骨を上下、左右、内回し、外回しに動かす | 10回ずつ |
アイソメトリック収縮 | 壁に手をつき、押し付けるように力を入れる(5秒キープ) | 5~10 |
2.2 慢性期(痛みが落ち着いてきた時期)の筋トレ方法
慢性期は、急性期に比べて痛みは軽減しますが、関節の動きが悪くなっている時期です。この時期は、可動域を広げるためのストレッチと、筋力強化のための筋トレをバランスよく行うことが大切です。
2.2.1 可動域を広げるための筋トレ
慢性期に入り、痛みが落ち着いてきたら、徐々に可動域を広げる運動を取り入れていきましょう。ただし、痛みが出ない範囲で行うことが重要です。
筋トレ | 方法 | 回数 |
腕を上げる運動 | 壁に手をつけ、少しずつ上に滑らせていく。無理のない範囲で上げる。 | 痛みの出ない範囲で |
後ろで手を組む運動 | 背中で手を組み、徐々に上に上げていく。 | 痛みの出ない範囲で |
外旋運動 | 肘を90度に曲げ、脇を締めたまま、前腕を外側に開いていく。 | 痛みの出ない範囲で |
2.2.2 筋力強化のための筋トレ
関節の動きが改善してきたら、筋力強化のための筋トレを行いましょう。チューブトレーニングや軽いダンベルを用いたトレーニングが効果的です。ただし、無理な負荷をかけると症状が悪化する可能性があるので、軽めの負荷から始め、徐々に負荷を上げていくようにしましょう。
筋トレ | 方法 | 回数 |
チューブを使った外旋運動 | チューブを固定し、肘を90度に曲げた状態でチューブを外側に引っ張る。 | 10~15 |
チューブを使った内旋運動 | チューブを固定し、肘を90度に曲げた状態でチューブを内側に引っ張る。 | 10~15 |
ダンベルを使った挙上運動 | 軽いダンベルを持ち、ゆっくりと腕を上げていく。 | 10~15 |
これらの筋トレはあくまでも一例です。ご自身の状態に合わせて、適切な筋トレを選択することが大切です。また、痛みがある場合は無理せず中止し、専門家に相談しましょう。
3. 自宅でできる簡単ストレッチ

五十肩の痛みや可動域制限を和らげるためには、自宅でできる簡単なストレッチも効果的です。無理のない範囲で行い、痛みを感じたらすぐに中止しましょう。
3.1 タオルを使ったストレッチ
タオルを使ったストレッチは、肩甲骨の動きを改善し、肩関節の柔軟性を高めるのに役立ちます。
3.1.1 タオルを使ったストレッチ1:肩の上げ下げ
両手でタオルの端を持ち、頭上に伸ばします。できる範囲で肘を曲げ、タオルを背中に下ろします。この動作をゆっくりと繰り返します。肩甲骨を意識して動かすことで、より効果的にストレッチできます。
3.1.2 タオルを使ったストレッチ2:肩の回旋
両手でタオルの両端を持ち、体の前で水平に伸ばします。そのまま腕を大きく回します。前回し、後ろ回しそれぞれ行いましょう。肩の筋肉をリラックスさせながら行うことが大切です。
3.2 壁を使ったストレッチ
壁を使ったストレッチは、肩関節の可動域を広げるのに効果的です。壁を使うことで、適切な角度を保ちながらストレッチできます。
3.2.1 壁を使ったストレッチ1:腕の上げ下げ
壁に手をつけ、指を壁に沿って上に滑らせます。痛みを感じない範囲で、できるだけ高く上げていきましょう。肩甲骨を意識しながら行うことで、効果的に肩関節の可動域を広げることができます。
3.2.2 壁を使ったストレッチ2:腕の水平移動
壁に手を肩の高さでつけ、横に滑らせます。痛みを感じない範囲で、できるだけ遠くまで手を伸ばしましょう。左右均等に行うように心がけてください。
3.3 椅子を使ったストレッチ
椅子を使ったストレッチは、安定した姿勢でストレッチを行うことができるため、安全かつ効果的に行うことができます。
3.3.1 椅子を使ったストレッチ1:肩甲骨回し
椅子に浅く腰掛け、背筋を伸ばします。両手を肩に置き、肘で円を描くように前後に回します。肩甲骨周りの筋肉をほぐすように意識して行いましょう。
3.3.2 椅子を使ったストレッチ2:体側伸ばし
椅子に浅く腰掛け、片手を頭の後ろに回し、もう片方の手で肘を持ちます。そのまま体を横に倒し、体側を伸ばします。呼吸を止めずにゆっくりと行うことがポイントです。
ストレッチの種類 | 効果 | 注意点 |
タオルを使ったストレッチ | 肩甲骨の動き改善、肩関節の柔軟性向上 | 痛みを感じない範囲で行う |
壁を使ったストレッチ | 肩関節の可動域拡大 | 無理に伸ばさない |
椅子を使ったストレッチ | 安定した姿勢でのストレッチ、体幹強化 | 姿勢を崩さない |
これらのストレッチは、五十肩の症状緩和に役立ちますが、痛みが強い場合は無理に行わず、専門家に相談することをお勧めします。また、ストレッチを行う際は、呼吸を止めずにゆっくりと行うことが大切です。これらのストレッチと鍼灸を組み合わせることで、より効果的に五十肩の改善が期待できます。
4. 鍼灸との併用で効果アップ

五十肩の改善には、筋トレやストレッチだけでなく、鍼灸を取り入れるのもおすすめです。鍼灸治療は、東洋医学に基づいた施術であり、五十肩の症状緩和に効果が期待できます。
ここでは、鍼灸が五十肩にどのように作用するのか、そして筋トレやストレッチとの併用によるメリットについて解説します。
4.1 鍼灸が五十肩に効果的な理由
鍼灸治療は、肩関節周囲の筋肉の緊張を緩和し、血行を促進することで、五十肩の痛みや炎症を抑える効果が期待できます。具体的には、以下の3つのメカニズムが考えられます。
筋肉の緊張緩和:鍼刺激が筋肉の緊張を和らげ、肩関節の動きをスムーズにする効果が期待できます。
血行促進:鍼やお灸の温熱刺激により血行が促進され、肩関節周囲の組織への酸素や栄養供給が向上し、炎症の抑制や治癒促進に繋がります。
鎮痛効果:鍼刺激によってエンドルフィンなどの鎮痛物質が分泌され、痛みの軽減に繋がると考えられています。
これらの相乗効果により、五十肩の症状改善が期待できます。肩の痛みや可動域制限にお悩みの方は、鍼灸治療を試してみる価値があるでしょう。
4.2 鍼灸と筋トレ・ストレッチを組み合わせるメリット
鍼灸と筋トレ・ストレッチを組み合わせることで、より効果的に五十肩を改善できます。それぞれのメリットを活かし、相乗効果を生み出すことで、早期回復を目指せます。
施術 | メリット | 併用のメリット |
鍼灸 | ● 痛みの緩和 ● 炎症の抑制 ● 血行促進 ● 筋肉の緊張緩和 | ● 筋トレ・ストレッチを行いやすい状態を作る ● 施術効果の持続 |
筋トレ・ストレッチ | ● 肩関節の可動域改善 ● 筋力強化 ● 再発予防 | ● 鍼灸の効果を持続させる ● 自宅で継続的なケアが可能 |
鍼灸治療によって痛みが軽減されれば、肩を動かしやすくなり、筋トレやストレッチをスムーズに行うことができます。また、鍼灸で得られた効果を筋トレやストレッチで維持・向上させることも期待できます。鍼灸と筋トレ・ストレッチを併用することで、相乗効果が生まれ、五十肩の早期回復、再発予防に繋がります。
五十肩でお悩みの方は、鍼灸治療と並行して、自宅でできる簡単な筋トレやストレッチを実践してみましょう。
5. まとめ

五十肩は、肩関節周囲の炎症や組織の癒着によって引き起こされる痛みや運動制限を伴う症状です。放置すると日常生活に支障をきたす場合もあるため、適切なケアが重要です。本記事では、五十肩の症状や原因、なりやすい人の特徴を解説し、自宅でできる効果的な筋トレ方法とストレッチをご紹介しました。
五十肩の筋トレは、痛みがある急性期と痛みが落ち着いてきた慢性期で方法が異なります。急性期には無理に動かすと炎症を悪化させる可能性があるため、痛みを増悪させない範囲での gentle な運動が推奨されます。慢性期には、肩関節の可動域を広げ、筋力を強化するための筋トレが効果的です。タオルや壁、椅子などを活用したストレッチも、肩周りの筋肉をほぐし、柔軟性を高めるのに役立ちます。
さらに、鍼灸治療を併用することで、五十肩の症状改善を促進できる可能性があります。鍼灸は、筋肉の緊張を緩和し、血行を促進することで、炎症を抑え、痛みの軽減に繋がると考えられています。筋トレやストレッチと組み合わせることで、相乗効果が期待できます。
五十肩でお悩みの方は、これらの方法を参考に、ご自身の状態に合ったケアを実践してみてください。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
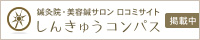




コメント