五十肩、温める?冷やす?どっちがいいの?鍼灸師が効果的な方法を徹底解説!
- 鍼灸院 横浜文庫
- 4月17日
- 読了時間: 16分
更新日:4月18日

「五十肩って温めた方がいいの?冷やした方がいいの?」と悩んでいませんか?
つらい五十肩の痛み、適切なケアをしないと悪化してしまうこともあります。実は、五十肩の痛みに対する温冷療法は、時期によって適切な方法が異なります。
この記事では、五十肩のメカニズムや痛みの原因、そして時期に合わせた温め方・冷やし方、その効果的な方法を鍼灸師の視点から分かりやすく解説します。
五十肩の症状に合わせたセルフケアや生活習慣の改善方法、鍼灸治療による改善策などもご紹介。適切なケアで一日も早く痛みから解放され、快適な生活を取り戻しましょう。
1. 五十肩とはどんな症状?

五十肩は、正式には「肩関節周囲炎」と呼ばれ、肩関節とその周囲の筋肉や腱、靭帯などに炎症が起こり、痛みや動きの制限が生じる疾患です。40代から50代に多く発症することから「五十肩」と呼ばれていますが、実際には30代や60代以降でも発症する可能性があります。
明確な原因が特定できない場合も多く、一次性肩関節周囲炎と呼ばれます。一方、外傷や骨折、腱板断裂、石灰沈着性腱板炎などが原因で発症する場合は二次性肩関節周囲炎と呼ばれます。
1.1 五十肩のメカニズム
五十肩のメカニズムは複雑で、まだ完全には解明されていません。しかし、肩関節周囲の組織の炎症、滑液包の炎症、関節包の萎縮や癒着などが原因と考えられています。加齢に伴う肩関節周囲の組織の老化や血行不良、肩関節の使い過ぎや運動不足なども発症に関与していると考えられています。
1.2 五十肩になりやすい人の特徴
五十肩になりやすい人の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。
特徴 | 詳細 |
年齢 | 40代~50代に最も多く発症します。 |
性別 | 女性に多く見られます。 |
生活習慣 | デスクワークなど、長時間同じ姿勢で作業をする人に多く見られます。 |
既往歴 | 糖尿病、甲状腺機能低下症などの持病がある人は発症リスクが高まります。 |
その他 | ストレスや睡眠不足なども影響すると考えられています。 |
これらの特徴に当てはまるからといって必ずしも五十肩になるわけではありませんが、注意が必要です。日常生活で肩に負担をかけないように意識し、適度な運動を心がけることが大切です。
2. 五十肩の痛みの原因

五十肩の痛みは、その進行段階によって原因が変化します。大きく分けて炎症期、凍結期、融解期の3つの時期があり、それぞれ異なる特徴があります。
2.1 炎症期
五十肩の初期段階である炎症期は、激しい痛みを伴うのが特徴です。肩関節の滑液包や関節包といった組織に炎症が生じることで、強い痛みを感じます。この時期の痛みは、夜間や安静時にも強く現れることが多く、睡眠を妨げることもあります。
また、肩を動かすと痛みが激しくなるため、肩の可動域が制限されます。炎症の原因としては、加齢による組織の老化や、肩への負担の蓄積、血行不良などが考えられます。
特に、日常生活で同じ動作を繰り返したり、長時間同じ姿勢を続けたりすることで、肩関節に負担がかかり、炎症を引き起こしやすくなります。
2.2 凍結期
炎症期の後には、凍結期に入ります。この時期は、炎症は治まりつつあるものの、肩関節周囲の組織が硬くなり、癒着が生じている状態です。そのため、強い痛みは軽減されますが、肩の可動域が著しく制限されます。腕を上げたり、後ろに回したりといった動作が困難になり、日常生活にも支障をきたすようになります。
痛みは動かさなければ感じにくいですが、動かそうとすると強い痛みを感じます。この凍結期は数ヶ月から半年、場合によってはそれ以上続くこともあります。
2.3 融解期
凍結期を過ぎると、徐々に肩関節の動きが回復していく融解期に入ります。肩関節周囲の組織の硬さが徐々に改善され、癒着も剥がれていくため、可動域が広がっていきます。
痛みも軽減し、日常生活動作もスムーズに行えるようになっていきます。ただし、完全に元の状態に戻るまでには時間がかかる場合もあり、個人差があります。焦らずにリハビリテーションを続けることが重要です。
時期 | 期間 | 症状 | 原因 |
炎症期 | 約2週間~3ヶ月 | 強い痛み、夜間痛、可動域制限 | 滑液包炎、腱板炎など |
凍結期 | 約4ヶ月~6ヶ月 | 痛みは軽減、可動域制限が強い | 関節包の癒着、拘縮 |
融解期 | 約6ヶ月~2年 | 痛みと可動域制限が徐々に改善 | 癒着の解消、組織の修復 |
五十肩の痛みは、これらの時期を通して変化していきます。それぞれの時期に合わせた適切なケアを行うことが、早期回復への鍵となります。自己判断せず、専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。
3. 五十肩に温めるのは効果的?

五十肩の痛みには、温める、冷やす、どちらが良いのでしょうか。
3.1 温めることのメリット
温めることで血行が促進され、筋肉や関節の緊張が和らぎます。これは、五十肩の痛みの緩和に繋がります。 また、温めることで新陳代謝が活発になり、組織の修復も促されます。
3.2 温める場合の注意点
温める場合は、熱すぎない温度に注意しましょう。熱すぎる温度で温めると、やけどの危険があります。
また、温めた後に冷やさないようにすることも大切です。急激な温度変化は、五十肩の症状を悪化させる可能性があります。
3.3 おすすめの方法:温湿布
五十肩に温める方法として、手軽で効果的なのが温湿布です。温湿布は、ドラッグストアなどで手軽に購入できます。温湿布には、血行促進効果のある成分が含まれており、肩の痛みやこわばりを和らげる効果が期待できます。温湿布は、肩に直接貼ることで、じんわりと温かさを感じることができます。
3.3.1 温湿布の効果的な使い方
温湿布を使用する際には、必ず使用方法をよく読んでから使用しましょう。貼る時間は、製品によって異なりますが、一般的には4時間程度です。長時間貼り続けると、かぶれなどの皮膚トラブルを起こす可能性がありますので、注意が必要です。
また、同じ場所に何度も繰り返し貼らないようにしましょう。皮膚への負担を軽減するために、貼る場所を少しずつずらすと良いでしょう。入浴時は、温湿布をはがしてから入浴するようにしてください。温湿布の種類によっては、入浴時に使用できるものもありますので、製品の使用方法をよく確認しましょう。蒸気温熱シートもおすすめです。温熱効果で患部を温め、血行を促進します。
4. 五十肩に冷やすのは効果的?

五十肩の痛みや炎症に、冷やすのは効果的なのでしょうか。
4.1 冷やすことのデメリット
冷やすことは、あまりおすすめされません。血行が悪くなり、筋肉が硬くなってしまう可能性があります。そのため、冷やす時間や方法には注意が必要です。
5. 五十肩の急性期、慢性期 温める?冷やす?どっちがいい?

五十肩の痛みや症状は、経過する時期によって大きく変化します。そのため、温める、冷やすといった対処法も、その時期に合わせた適切な方法を選択することが重要です。
五十肩の進行は、大きく分けて急性期、慢性期、回復期に分けられますが、回復期は症状が軽減していく時期のため、ここでは急性期と慢性期について詳しく解説します。
5.1 急性期の対処法
急性期は、発症から約2週間程度の期間で、炎症が強く出ている時期です。この時期の特徴は、強い痛みと関節の動きの制限です。少し動かしただけでも激痛が走り、夜も眠れないほどの痛みを感じる方もいます。腕を上げる、後ろに回すといった動作が困難になります。
無理に温める必要もありませんが過度に冷やすのはあまりおすすめされません。
5.2 慢性期の対処法
慢性期は、発症から約3週間~数ヶ月程度の期間で、痛みはやや軽減しますが、関節の動きが制限された状態が続きます。この時期の特徴は、強い痛みはないものの、腕が上がらない、後ろに回せないなどの運動制限が続くことです。肩関節周囲の筋肉が硬くなり、関節の動きが悪くなっている状態です。朝起きた時や、長時間同じ姿勢を続けた後に、肩の stiffness(こわばり)を感じることがあります。
慢性期では、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる温めることが効果的です。温めることで、肩関節周囲の筋肉が柔らかくなり、動きの改善が期待できます。
方法 | 効果 | 注意点 |
温湿布 | 血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる | 同じ場所に長時間貼らない(低温やけどの恐れがあるため) かぶれなどに注意 |
ホットタオル | 手軽に温めることができる | やけどに注意 濡れたタオルを電子レンジで温める場合は、加熱時間を短くし様子を見ながら行う |
温浴 | 全身を温め、リラックス効果も得られる | 長湯は避ける 入浴後、体が冷えないように注意 |
6. 鍼灸治療で五十肩を改善する方法

五十肩でお悩みの方の中には、鍼灸治療に興味を持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。一体どのような効果が期待できるのか、詳しく見ていきましょう。
6.1 鍼灸が五十肩に効果的な理由
鍼灸治療は、肩関節周囲の筋肉の緊張を緩和し、血行を促進することで、五十肩の痛みや可動域制限の改善に効果が期待できます。東洋医学では、五十肩は「気」「血」「水」の滞りによって引き起こされると考えられています。鍼灸治療は、これらの流れをスムーズにすることで、身体の自然治癒力を高め、症状の改善を促すとされています。
西洋医学的には、鍼刺激が神経伝達物質であるエンドルフィンやセロトニンの分泌を促進し、鎮痛効果を発揮すると考えられています。また、トリガーポイントと呼ばれる筋肉の硬結に鍼を刺入することで、筋肉の緊張を緩和し、痛みの軽減につながります。
6.2 五十肩への鍼灸治療の方法
五十肩への鍼灸治療では、肩関節周囲のツボだけでなく、全身の状態を診て、関連するツボにも鍼やお灸を施します。代表的なツボとしては、肩髃(けんぐう)、肩井(けんせい)、天宗(てんそう)、缺盆(けつぼん)などがあります。これらのツボに鍼やお灸をすることで、肩関節周囲の血行を促進し、筋肉の緊張を緩和します。
治療法 | 作用 | 五十肩への効果 |
鍼治療 | 筋肉の緊張緩和、血行促進、鎮痛効果 | 痛み軽減、可動域改善 |
灸治療 | 温熱効果、血行促進、免疫力向上 | 痛み軽減、炎症抑制、治癒促進 |
鍼治療は、髪の毛ほどの細い鍼をツボに刺入するため、痛みはほとんど感じません。また、灸治療は、もぐさを燃焼させて温熱刺激を与えるため、心地よい温かさを感じます。施術時間は、症状や体質によって異なりますが、おおむね30分~1時間程度です。
6.3 治療頻度と期間の目安
五十肩の鍼灸治療の頻度は、症状の程度によって異なりますが、一般的には週に1~2回程度が目安です。急性期は集中的に治療を行い、症状が落ち着いてきたら徐々に頻度を減らしていきます。治療期間は、個人差がありますが、数週間から数ヶ月かかる場合もあります。早期に治療を開始することで、症状の悪化を防ぎ、回復を早めることができます。
鍼灸治療は、五十肩の痛みや可動域制限の改善に効果的な方法ですが、すべての人に効果があるとは限りません。また、他の治療法と併用することで、より効果を高めることができます。五十肩でお悩みの方は、一度鍼灸師に相談してみることをおすすめします。
7. 五十肩のセルフケア方法

五十肩の痛みを和らげ、回復を促すためには、セルフケアが重要です。適切なセルフケアを行うことで、症状の悪化を防ぎ、日常生活の質を向上させることができます。ここでは、五十肩に効果的なセルフケアの方法として、ストレッチ、マッサージ、ツボ押しについて解説します。
7.1 ストレッチ
五十肩のストレッチは、肩関節の可動域を広げ、筋肉の柔軟性を高める効果があります。痛みを感じない範囲で、無理なく行うことが大切です。毎日継続して行うことで、効果を実感しやすくなります。
7.1.1 肩甲骨回し
肩甲骨を上下、左右、前後に動かすことで、肩周りの筋肉をほぐします。肩甲骨を意識的に動かすことで、肩関節の可動域を広げることができます。
7.1.2 腕の振り子運動
体を前かがみにし、リラックスした状態で腕を前後に、左右に振ります。遠心力を使って腕を振ることで、肩関節への負担を軽減しながらストレッチできます。
7.1.3 タオルを使ったストレッチ
タオルの両端を持ち、背中の後ろで上下に動かします。タオルを使うことで、肩関節の可動域を広げやすくなります。
7.2 マッサージ
五十肩のマッサージは、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。入浴後など、体が温まっている時に行うのが効果的です。
7.2.1 肩周りのマッサージ
肩の筋肉を指で優しく揉みほぐします。痛みを感じる場合は、無理に行わず、優しく触れる程度にしましょう。
7.2.2 首周りのマッサージ
首の筋肉が緊張していると、肩の痛みを悪化させることがあります。首の後ろから肩にかけて、優しくマッサージします。首の付け根から肩にかけて丁寧にマッサージすることで、肩こりの改善にも繋がります。
7.3 ツボ押し
五十肩に効果的なツボを刺激することで、痛みを和らげ、回復を促すことができます。ツボ押しは、いつでもどこでも手軽に行えるセルフケアです。
ツボの名前 | 位置 | 効果 |
肩井(けんせい) | 首の付け根と肩先の中間点 | 肩こり、肩の痛みを和らげる |
天宗(てんそう) | 肩甲骨の真ん中あたり | 肩甲骨周りの筋肉の緊張を和らげる |
曲池(きょくち) | 肘を曲げた時にできるシワの外側 | 肩の痛み、腕の痺れを和らげる |
ツボ押しは、息を吐きながら3~5秒ほど押すのが効果的です。痛みを感じる場合は、無理に押さないようにしましょう。
これらのセルフケアは、五十肩の症状緩和に役立ちますが、痛みが強い場合や症状が改善しない場合は、鍼灸院への相談も検討しましょう。専門家による適切な治療を受けることで、より効果的に症状を改善することができます。
8. 五十肩を悪化させないための生活習慣

五十肩の痛みや不快感を悪化させないためには、日常生活での適切なケアが重要です。正しい姿勢、質の高い睡眠、そして適切な運動を心がけることで、症状の進行を抑え、回復を促進することができます。
8.1 姿勢
猫背や前かがみの姿勢は、肩関節への負担を増大させ、五十肩の症状を悪化させる可能性があります。常に正しい姿勢を意識することで、肩への負担を軽減し、痛みの悪化を防ぐことができます。
8.1.1 正しい姿勢のポイント
● 背筋を伸ばす:背筋を伸ばし、頭が体の中心にくるように意識します。
● 肩甲骨を寄せる:肩甲骨を背骨に寄せるように意識することで、胸が開き、肩への負担が軽減されます。
● 顎を引く:顎を引くことで、首の負担を軽減し、肩への負担も軽減されます。
デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続ける場合は、こまめに休憩を取り、軽いストレッチを行うようにしましょう。また、パソコンのモニターの高さを調整する、椅子にクッションを置くなど、作業環境を整えることも重要です。
8.2 睡眠
質の高い睡眠は、体の回復を促し、五十肩の症状改善にも繋がります。睡眠不足は、筋肉の緊張を高め、痛みを悪化させる可能性があります。 睡眠時間をしっかりと確保し、快適な睡眠環境を整えることが大切です。
8.2.1 質の高い睡眠のためのポイント
● 適切な睡眠時間:個人差はありますが、7時間程度の睡眠時間を確保するようにしましょう。
● 寝る前のカフェイン摂取を控える:カフェインは睡眠の質を低下させるため、寝る前のコーヒーや紅茶は控えましょう。
● 快適な寝具を選ぶ:自分に合った枕や布団を選ぶことで、睡眠の質を向上させることができます。特に、肩に負担がかからない寝具を選ぶことが重要です。
● 寝る前にリラックスする:ぬるめのお風呂に入ったり、リラックス効果のある音楽を聴いたりするなど、寝る前にリラックスする時間を取りましょう。
8.3 運動
五十肩の痛みがあるからといって、全く動かさないでいると、肩関節の可動域が狭まり、症状が悪化することがあります。痛みのない範囲で、肩関節を動かす運動を取り入れることが大切です。
8.3.1 五十肩におすすめの運動
運動の種類 | 効果 | 注意点 |
振り子運動 | 肩関節の可動域を広げる | 痛みを感じない範囲で行う |
タオル体操 | 肩甲骨の動きを改善する | 無理に伸ばさない |
壁登り運動 | 肩関節の柔軟性を高める | 痛みを感じたらすぐに中止する |
これらの運動は、痛みを感じない範囲で、無理なく行うことが重要です。痛みがある場合は、運動を中止し、安静にするようにしましょう。また、運動を行う前に、温湿布やホットタオルなどで肩を温めると、筋肉がリラックスし、運動がしやすくなります。
これらの生活習慣を改善することで、五十肩の症状悪化を予防し、より快適な生活を送ることができます。 継続して取り組むことが大切です。
9. 五十肩におすすめの市販薬

五十肩の痛みや炎症を抑えるために、市販薬を利用することもできます。適切な市販薬を選ぶことで、症状の緩和が期待できます。ここでは、五十肩におすすめの市販薬の種類と選び方、そして注意点について解説します。
9.1 痛み止め
五十肩の痛みには、アセトアミノフェンを主成分とする鎮痛薬がおすすめです。アセトアミノフェンは、胃腸への負担が少ないため、比較的安心して服用できます。タイレノールAやノーシンなどが代表的な製品です。用法・用量を守って服用しましょう。
9.2 消炎鎮痛剤
五十肩の炎症や痛みを抑えるには、イブプロフェンやロキソプロフェンナトリウムなどの成分を含む消炎鎮痛剤が有効です。イブA錠、ロキソニンS、バファリンAなど、様々な製品が市販されています。これらの薬は、炎症を抑えることで痛みを軽減する効果が期待できます。
ただし、胃腸への負担がある場合があるので、空腹時の服用は避け、用法・用量を守ることが大切です。
9.2.1 外用薬
飲み薬だけでなく、塗り薬タイプの消炎鎮痛剤も効果的です。インドメタシンやフェルビナクを配合したボルタレンEX、アンメルツゴールドEXなどが市販されています。患部に直接塗布することで、局所的に痛みや炎症を抑えることができます。また、温感タイプの塗り薬には、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。
9.3 湿布薬
温湿布と冷湿布、どちらが良いのか迷う方もいるかもしれません。急性期で炎症が強い場合は、冷湿布を使用し、慢性期で血行不良が原因となっている場合は、温湿布を使用するのが一般的です。症状に合わせて使い分けましょう。
種類 | 効果 | 代表的な商品 |
冷湿布 | 炎症を抑える、痛みを和らげる | パスタイムFX7、ニューパスA |
温湿布 | 血行を促進する、筋肉の緊張を和らげる | フェイタスZαジクサス、サロンパス |
市販薬を選ぶ際には、自分の症状に合った薬を選ぶことが重要です。また、持病がある方や他の薬を服用している方は、医師や薬剤師に相談してから使用するようにしましょう。自己判断で服用すると、思わぬ副作用が出る可能性があります。用法・用量を守り、適切に使用することで、五十肩の症状を効果的に緩和することができます。
10. まとめ

五十肩は、肩関節周囲の炎症や組織の癒着によって引き起こされる痛みやしびれを伴う症状です。その痛みは、炎症期、凍結期、融解期と段階的に変化していきます。 それぞれの時期によって適切な対処法が異なり、自己判断は禁物です。
炎症期の急性痛には、炎症を抑えるために冷湿布を使用するのが効果的です。逆に、慢性期の凍結期、融解期には、血行促進のために温湿布が有効です。ただし、温めすぎや冷やしすぎは逆効果になる可能性があるので、適切な時間と温度を守るようにしましょう。痛みが強い場合は、無理に動かさず安静にすることが大切です。
五十肩の改善には、鍼灸治療も効果的です。鍼灸は、肩関節周囲の血行を促進し、筋肉の緊張を緩和することで、痛みやしびれを軽減します。ストレッチやマッサージ、ツボ押しなどのセルフケアも効果的ですが、症状に合わせた適切な方法で行うことが重要です。五十肩を予防するためには、正しい姿勢や質の良い睡眠、適度な運動などの生活習慣を心がけましょう。
つらい五十肩の痛みでお悩みの方は、当院へご相談ください。
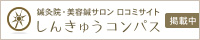




コメント