五十肩に鍼灸は効果あり?症状・原因・治療法を専門家が徹底解説
- 鍼灸院 横浜文庫
- 2月18日
- 読了時間: 15分
更新日:12月7日

つらい五十肩の痛み、どうすればいいか悩んでいませんか? 夜も眠れないほどの痛みや、腕が上がらない不便さに困っている方もいるかもしれません。
このページでは、五十肩の症状や原因、一般的な治療法に加え、鍼灸治療が五十肩に効果的な理由を詳しく解説します。鍼灸治療のメカニズムや、他の治療法との併用についても分かりやすく説明しているので、鍼灸治療に興味がある方は必見です。
さらに、鍼灸院での治療の流れや、治療を受ける際の注意点、自宅でできるセルフケアの方法まで網羅的にご紹介します。五十肩の痛みを和らげ、快適な日常生活を取り戻すためのヒントが満載です。
この記事を読めば、五十肩に対する理解が深まり、自分に合った治療法を見つけるための一助となるでしょう。
1. 五十肩とは

五十肩とは、正式には肩関節周囲炎と呼ばれる、肩関節の痛みと動きの制限を特徴とする疾患です。40代から50代に多く発症することから、五十肩と呼ばれていますが、実際には30代や60代以降に発症することもあります。
肩関節周囲の筋肉や腱、靭帯、関節包などが炎症を起こしたり、癒着したりすることで、肩の痛みや動かしにくさが生じます。自然に治癒するケースもありますが、適切な治療を行わないと痛みが慢性化したり、関節の可動域が狭くなって日常生活に支障をきたす場合もあります。
1.1 五十肩の症状
五十肩の主な症状は、肩の痛みと動きの制限です。痛みは、肩関節周囲に鈍くうずくような痛みや、特定の動作で鋭く刺すような痛みなど、様々な形で現れます。また、夜間や安静時に痛みが強くなることもあります。
動きの制限は、腕を上げたり、後ろに回したり、外側に広げたりする動作が困難になることで、日常生活に大きな影響を与えます。具体的には、服を着替えたり、髪を洗ったり、高いところに手が届かなくなったりするなどの不便が生じます。
1.2 五十肩の原因
五十肩の明確な原因は、まだ完全には解明されていません。しかし、加齢に伴う肩関節周囲の組織の老化や、肩関節の使い過ぎ、外傷、不良姿勢、冷え、ストレスなどが発症に関与していると考えられています。
また、糖尿病や甲状腺機能低下症などの基礎疾患が、五十肩のリスクを高める要因となる場合もあります。
原因 | 詳細 |
加齢 | 肩関節周囲の組織の老化により、炎症や損傷が起こりやすくなります。 |
肩関節の使い過ぎ | スポーツや仕事などで肩関節を過度に使用することで、炎症や損傷のリスクが高まります。 |
外傷 | 転倒や打撲などによって肩関節を損傷すると、五十肩を発症することがあります。 |
不良姿勢 | 猫背などの不良姿勢は、肩関節周囲の筋肉や靭帯に負担をかけ、五十肩のリスクを高めます。 |
冷え | 冷えによって肩関節周囲の血行が悪くなると、炎症や痛みが悪化することがあります。 |
ストレス | ストレスは、筋肉の緊張を高め、肩関節の動きを制限する原因となります。 |
基礎疾患 | 糖尿病や甲状腺機能低下症などの基礎疾患は、五十肩のリスクを高める要因となります。 |
これらの要因が複合的に作用して、五十肩を発症すると考えられています。
特に、加齢に伴う変化は、五十肩の大きな要因の一つです。加齢により、肩関節周囲の組織は弾力性を失い、炎症や損傷が起こりやすくなります。
また、修復機能も低下するため、一度炎症が起こると治りにくく、慢性化しやすい傾向があります。
2. 五十肩の一般的な治療法

五十肩の治療は、その症状の程度や経過、個々の状態に合わせて行われます。保存療法が中心となり、多くの場合、手術は必要ありません。
主な治療法としては、薬物療法、理学療法、その他注射療法などがあります。
2.1 薬物療法
痛みや炎症を抑えることを目的として、様々な薬が用いられます。
2.1.1 経口薬
痛みや炎症を抑えるために、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が一般的に使用されます。ロキソプロフェンナトリウムやイブプロフェンなどが代表的な薬です。胃腸への負担を軽減したタイプもあります。
また、痛みを抑える作用の強いアセトアミノフェンも用いられます。
2.1.2 外用薬
患部に直接塗布することで、痛みや炎症を和らげる効果が期待できます。インドメタシンやジクロフェナクナトリウムなどを含む軟膏やクリーム、湿布薬などがあります。経口薬と併用することもあります。
2.2 理学療法
五十肩の治療において、理学療法は非常に重要な役割を担います。肩関節の可動域を改善し、機能回復を目指すための様々な運動療法や物理療法があります。
2.2.1 運動療法
種類 | 内容 | 効果 |
ストレッチ | 肩関節周囲の筋肉の柔軟性を高めるための運動。タオルを使ったストレッチや、壁や机を利用したストレッチなど、様々な方法があります。 | 肩の可動域を広げ、痛みを軽減する効果があります。 |
筋力トレーニング | 肩関節周囲の筋肉を強化するための運動。チューブや軽いダンベルなどを用いたトレーニングや、自重を使ったトレーニングなどがあります。 | 肩関節の安定性を高め、再発予防に効果があります。 |
関節モビライゼーション | 徒手的に関節を動かすことで、関節の動きを滑らかにする療法。 | 関節の拘縮を改善し、可動域を広げる効果があります。 |
2.2.2 物理療法
温熱療法、冷却療法、電気刺激療法などがあります。温熱療法は血流を促進し、筋肉の緊張を緩和する効果があり、冷却療法は炎症や痛みを抑える効果があります。
電気刺激療法は、痛みを軽減する効果が期待できます。
2.3 その他注射療法
痛みが強い場合や、他の治療法で効果が見られない場合に、注射療法が行われることがあります。
2.3.1 関節内注射
肩関節内にヒアルロン酸を注射することで、関節の動きを滑らかにし、痛みを軽減する効果が期待できます。また、ステロイド注射を行う場合もあります。炎症を抑える効果は高いですが、副作用のリスクもあるため、慎重に判断されます。
これらの治療法は単独で行われることもありますが、複数の治療法を組み合わせることで、より効果的な治療となる場合もあります。症状や状態に合わせて適切な治療法を選択することが重要です。
3. 鍼灸が五十肩に効果的な理由

五十肩でお悩みの方にとって、鍼灸治療は魅力的な選択肢の一つと言えるでしょう。
西洋医学的な治療法とは異なるアプローチで、肩の痛みや動きの制限といった症状に効果を発揮することが期待できます。
ここでは、鍼灸が五十肩に効果的な理由を、メカニズムや他の治療法との併用といった観点から詳しく解説していきます。
3.1 鍼灸による疼痛緩和のメカニズム
鍼灸治療は、肩周辺の筋肉や組織に鍼を刺入することで、様々な生理的な反応を引き起こし、疼痛緩和に繋がると考えられています。
具体的には、以下のメカニズムが関与していると考えられています。
ゲートコントロールセオリー:鍼刺激が神経を刺激することで、痛みの信号を脳に伝える経路を抑制し、疼痛の感覚を軽減すると考えられています。
エンドルフィン分泌促進:鍼刺激によって脳内でエンドルフィンという神経伝達物質の分泌が促進されます。エンドルフィンはモルヒネに似た鎮痛作用を持つため、痛みを和らげる効果が期待できます。
血行促進作用:鍼を刺入することで、肩周辺の血行が促進されます。血行が良くなることで、筋肉や組織への酸素供給が向上し、老廃物の排出も促進され、痛みの軽減や治癒促進に繋がると考えられています。
3.2 五十肩に伴う炎症や拘縮への鍼灸の効果
五十肩は、肩関節周囲の炎症や拘縮(関節が硬くなること)を伴うことが多く、これが痛みや動きの制限の原因となります。
鍼灸治療は、これらの症状にも効果を発揮すると考えられています。
症状 | 鍼灸の効果 |
炎症 | 鍼刺激が炎症を鎮める物質の分泌を促進し、炎症を抑える効果が期待できます。 |
拘縮 | 鍼刺激によって筋肉の緊張が緩和され、関節の可動域が広がり、拘縮の改善に繋がると考えられています。 |
3.3 鍼灸と他の治療法との併用
鍼灸治療は、他の治療法と併用することで、より効果を高めることができると考えられています。例えば、理学療法と組み合わせることで、肩関節の可動域改善を促進したり、薬物療法と併用することで、鎮痛効果を高めることが期待できます。
五十肩の症状や原因、体質は人それぞれ異なるため、鍼灸治療の効果や施術内容も個別に調整されます。五十肩でお悩みの方は、鍼灸院に相談し、ご自身の状態に合った治療法を選択することが大切です。
4. 五十肩に対する鍼灸治療の実際

五十肩でお悩みの方にとって、鍼灸治療が具体的にどのようなものか、気になるところでしょう。ここでは、鍼灸院での五十肩治療の流れや頻度、期間、そして治療を受ける際の注意点などを詳しく解説します。
4.1 鍼灸院での五十肩治療の流れ
一般的な鍼灸院での五十肩治療の流れは以下の通りです。
問診と診察:現在の症状、既往歴、生活習慣などについて詳しくお聞きします。肩の動きや痛みの程度を確認するための触診も行います。
治療方針の説明:問診と診察の結果に基づいて、患者様一人ひとりに最適な治療方針を立て、ご説明します。治療内容や期間、費用などについてご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。
鍼灸治療の実施:肩関節周辺の筋肉やツボに鍼を刺したり、お灸を据えたりします。使用する鍼は使い捨てで、衛生管理も徹底していますのでご安心ください。
治療後の説明とアドバイス:治療後の状態を確認し、今後の治療計画や自宅でのセルフケアの方法などについてアドバイスを行います。日常生活で気を付ける点などもご説明します。
4.2 五十肩への鍼灸治療の頻度と期間
五十肩への鍼灸治療の頻度や期間は、症状の程度や個々の体質によって異なります。一般的な目安としては、初期段階では週に2~3回、痛みが軽減してきたら週に1~2回程度の治療が推奨されます。
治療期間は、数週間から数ヶ月かかる場合もあります。症状が改善してきたら、徐々に治療の間隔を空けていきます。
下記の表はあくまでも目安であり、個々の状況に合わせて調整されます。
症状の程度 | 治療頻度 | 治療期間の目安 |
急性期(痛みや炎症が強い時期) | 週2~3回 | 1~2ヶ月 |
慢性期(痛みや炎症が落ち着いてきた時期) | 週1~2回 | 2~3ヶ月 |
回復期(痛みがほとんどなく、可動域も回復してきた時期) | 月1~2回 | メンテナンスとして継続 |
4.3 鍼灸治療を受ける際の注意点
鍼灸治療を受ける際には、以下の点に注意しましょう。
空腹時や満腹時は避ける:治療前に食事を軽く済ませておくのが良いでしょう。食後すぐや空腹時は、気分が悪くなる可能性があります。
リラックスした服装で来院する:締め付けの強い服装は避け、ゆったりとした服装で来院してください。治療部位へのアクセスがスムーズになります。
治療前にアルコールを摂取しない:アルコールは血行を促進するため、鍼灸治療の効果に影響を与える可能性があります。治療前は飲酒を控えましょう。
治療後の入浴は控える:治療後は、体が温まっているため、入浴によって血行が促進されすぎると、めまいや立ちくらみを起こす可能性があります。当日の入浴は控え、シャワーで済ませるようにしましょう。
疑問や不安があれば相談する:治療に関する疑問や不安な点があれば、遠慮なく施術者に相談してください。納得した上で治療を受けることが大切です。
5. 五十肩の鍼灸治療に関するよくある質問

五十肩の鍼灸治療に関して、患者様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
5.1 鍼灸治療は痛いですか?
鍼治療で使用される鍼は、髪の毛ほどの非常に細いものです。注射針とは異なり、刺入時の痛みはほとんど感じません。人によっては、チクッとした感覚や鈍い痛みを感じることもありますが、我慢できないほどの痛みではありません。
また、灸治療は温熱刺激を与える治療法であり、やけどにならないよう細心の注意を払って行います。熱いと感じたらすぐに施術者に伝えましょう。
5.2 鍼灸治療の頻度はどのくらいですか?
五十肩の症状や経過によって異なりますが、一般的には週に1~2回程度の治療が推奨されます。症状が重い場合は、集中的に治療を行うこともあります。治療の頻度や期間については、施術者と相談しながら決定します。
5.3 鍼灸治療の効果はどれくらいで現れますか?
これも個人差がありますが、早い方では1回目の治療から効果を実感される方もいらっしゃいます。多くの場合、数回の治療で痛みの軽減や可動域の改善が見られます。
しかし、五十肩は慢性的な症状であるため、根本的な改善にはある程度の期間が必要です。焦らずに、継続して治療を受けることが大切です。
5.4 鍼灸治療を受けられない場合はありますか?
以下のような場合は、鍼灸治療を受けられない、もしくは注意が必要な場合があります。施術前に必ず施術者に相談しましょう。
状態 | 詳細 |
妊娠中 | 妊娠中は、特定のツボへの刺激を避ける必要があります。 |
出血しやすい病気 | 血友病など、出血しやすい病気の方は、鍼治療によって内出血を起こすリスクがあります。 |
感染症 | 感染症にかかっている場合は、症状が悪化する可能性があります。 |
ペースメーカーを使用している | ペースメーカーを使用している場合は、鍼灸治療の影響を受ける可能性があります。 |
金属アレルギー | 鍼の素材に金属が使用されているため、金属アレルギーの方は反応が出る可能性があります。 |
5.5 鍼灸治療と他の治療法を併用できますか?
はい、可能です。鍼灸治療は、他の治療法と併用することで、より効果を高めることができます。例えば、薬物療法や理学療法と組み合わせることで、相乗効果が期待できます。現在、他の治療を受けている場合は、施術者にその旨を伝えましょう。
5.6 五十肩の鍼灸治療で気を付けることはありますか?
治療後は、激しい運動や長時間の入浴は避け、安静にするように心がけましょう。また、十分な睡眠とバランスの取れた食事を摂ることも、五十肩の改善には重要です。
日常生活での注意点についても、施術者からアドバイスを受けるようにしましょう。
5.7 どの鍼灸院を選べば良いですか?
五十肩の治療実績が豊富で、しっかりと説明してくれる鍼灸院を選ぶことが大切です。ホームページなどで施術内容や院の雰囲気を確認したり、実際に来院して相談してみるのも良いでしょう。信頼できる施術者を見つけることが、五十肩の改善への第一歩です。
6. 五十肩のセルフケア

五十肩の症状緩和と回復促進には、専門家による施術と並行して、自宅でのセルフケアも非常に重要です。適切なセルフケアを行うことで、痛みの軽減、関節可動域の改善、再発予防に繋がります。無理のない範囲で行うことが大切で、痛みが増強する場合はすぐに中止し、施術者に相談しましょう。
6.1 自宅でできるストレッチや運動
五十肩のセルフケアで最も効果的なのは、肩関節周囲の筋肉を柔らかく保つためのストレッチと、関節の動きを滑らかにするための運動です。
下記にいくつか例を挙げますが、ご自身の状態に合わせて無理なく行いましょう。痛みを感じない範囲で、ゆっくりと呼吸をしながら行うのがポイントです。
ストレッチ/運動 | 方法 | 注意点 |
振り子運動 | 体を前かがみにし、リラックスした状態で腕を振り子のように前後に、左右に、そして円を描くように動かします。 | 勢いをつけすぎず、痛みが出ない範囲で小さく始め、徐々に大きくしていくようにしましょう。 |
タオルを使ったストレッチ | タオルの両端を持ち、背中に回し、上下に動かします。肩甲骨を動かすイメージで行いましょう。 | タオルを持つ手の幅を調整することで、ストレッチの強度を変えることができます。 |
壁を使ったストレッチ | 壁に手をつけ、指を壁に沿って少しずつ上に登らせていきます。肩甲骨を意識して、無理なく行いましょう。 | 痛みを感じたら無理せず、できる範囲で行いましょう。 |
肩甲骨はがしストレッチ | 両手を前に伸ばし、手のひらを合わせます。そのまま肘を曲げ、肩甲骨を寄せるように意識しながら、胸を前に突き出します。 | 肩甲骨周りの筋肉がほぐれるのを感じながら行いましょう。 |
鎖骨周辺のマッサージ | 鎖骨の上下を優しくマッサージします。血行促進効果が期待できます。 | 強く押しすぎないように注意しましょう。 |
これらのストレッチや運動は、1回につき5~10回程度、1日数回行うのが理想です。入浴後など、体が温まっている時に行うとより効果的です。重要なのは、継続することです。毎日続けることで、徐々に肩の動きがスムーズになり、痛みが軽減されていくのを実感できるでしょう。
6.2 日常生活での注意点
日常生活においても、五十肩を悪化させないための工夫が必要です。姿勢に気を配り、猫背にならないように意識しましょう。長時間同じ姿勢を続ける場合は、こまめに休憩を取り、肩を回したり、ストレッチを行うように心掛けましょう。また、重い荷物を持つ際は、できる限り両肩に均等に重さがかかるように工夫し、片方の肩に負担がかかりすぎないように注意しましょう。
冷えは五十肩の大敵です。特に冬場は、肩周りを冷やさないように、暖かい服装を心がけましょう。また、シャワーだけでなく、湯船に浸かって体を温めることも効果的です。血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。
睡眠時の姿勢にも気を配りましょう。患部を圧迫しないような姿勢で寝ることが大切です。横向きで寝る場合は、抱き枕などを使うと、肩への負担を軽減することができます。自分に合った寝具を選ぶことも重要です。
五十肩のセルフケアは、地道な努力が必要ですが、回復への大きな助けとなります。焦らず、ご自身のペースで継続していくことが大切です。
7. まとめ

五十肩は、中高年に多く発症する肩関節周囲炎です。肩の痛みや運動制限といった症状が現れ、日常生活に支障をきたすこともあります。その原因は、加齢による肩関節周囲の組織の老化や炎症などが考えられます。五十肩の治療法としては、薬物療法、理学療法、手術療法などがありますが、鍼灸も効果的な選択肢の一つです。
鍼灸治療は、肩周辺のツボに鍼を刺したり、お灸を据えることで、血行を促進し、筋肉の緊張を緩和する効果が期待できます。また、痛みを伝える神経経路を抑制することで、疼痛緩和にも繋がります。五十肩に伴う炎症や拘縮にも効果を発揮し、肩関節の可動域を広げる助けとなります。
他の治療法との併用も可能で、相乗効果が期待できるケースもあります。
鍼灸治療を受ける際には、国家資格を持つ鍼灸師のいる信頼できる鍼灸院を選びましょう。治療頻度や期間は症状によって異なりますが、継続的な治療が重要です。セルフケアとして、自宅でできるストレッチや運動、日常生活での注意点を守ることも大切です。
五十肩でお悩みの方は、鍼灸治療を検討してみてはいかがでしょうか。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
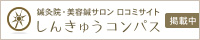




コメント