椎間板ヘルニアで足が痛い!その原因と鍼灸治療の効果・メカニズムを徹底解説
- 鍼灸院 横浜文庫
- 8月2日
- 読了時間: 15分

椎間板ヘルニアによる足の痛み、その原因と鍼灸治療との関係について悩んでいませんか?
この記事では、椎間板ヘルニアで足が痛くなるメカニズムを分かりやすく解説し、鍼灸治療が効果的な理由、その作用メカニズム、さらに予防法まで網羅的にご紹介します。
椎間板ヘルニアの構造や役割、神経根への圧迫、炎症、筋肉の緊張といった痛みの原因、坐骨神経痛などの症状、そして鍼灸治療による血行促進、鎮痛、筋肉の緩和、神経機能回復促進といった効果について詳しく説明します。
この記事を読むことで、椎間板ヘルニアによる足の痛みの原因を理解し、鍼灸治療が症状改善に役立つ可能性があることを知ることができます。そして、ご自身に合った適切な対処法を見つけるための一助となるでしょう。
1. 椎間板ヘルニアとは何か

椎間板ヘルニアは、背骨の構成要素である椎間板に生じる疾患です。腰や首に多く発生し、激しい痛みやしびれを引き起こすことがあります。
加齢や激しい運動、長時間のデスクワークなど、さまざまな要因が関係しています。
1.1 椎間板の構造と役割
椎間板は、背骨を構成する椎骨と椎骨の間に位置するクッションのような役割を果たす組織です。
弾力性のある髄核と呼ばれるゼリー状の中心部と、それを囲む線維輪と呼ばれる丈夫な組織からできています。
この構造により、椎間板は衝撃を吸収し、体の動きをスムーズにする役割を担っています。
椎間板のおかげで、私たちは体を曲げたり、ひねったり、ジャンプしたりといった動作をスムーズに行うことができるのです。
構成要素 | 役割 |
髄核 | ゼリー状の組織で、衝撃を吸収する。 |
線維輪 | 髄核を囲む丈夫な組織で、椎間板の形状を維持する。 |
1.2 椎間板ヘルニアの発生メカニズム
椎間板ヘルニアは、線維輪に亀裂が生じ、髄核が飛び出すことで発生します。
この飛び出した髄核が神経を圧迫することで、痛みやしびれなどの症状が現れます。
加齢とともに椎間板の水分が減少して弾力性が失われることで、線維輪が損傷しやすくなります。
また、重いものを持ち上げる、激しいスポーツをする、長時間同じ姿勢を続けるといった動作や習慣も、椎間板への負担を増大させ、ヘルニア発生のリスクを高めます。
その他、遺伝的な要因や喫煙なども影響すると考えられています。
2. 椎間板ヘルニアで足が痛くなる原因

椎間板ヘルニアになると、なぜ足が痛くなるのでしょうか。
その主な原因は、飛び出した椎間板による神経の圧迫、炎症の発生、そして筋肉の緊張です。これらの要素が複雑に絡み合い、痛みやしびれといった症状を引き起こします。
2.1 神経根への圧迫
椎間板ヘルニアで最も一般的な痛みの原因は、神経根への圧迫です。
椎間板の中心にある髄核が飛び出すと、周囲にある神経根を圧迫します。腰椎にヘルニアが生じた場合、坐骨神経が圧迫されることが多く、その結果、お尻から足にかけて痛みやしびれが生じます。
この痛みは、ヘルニアの大きさや位置、神経根への圧迫の程度によって様々です。
軽度の圧迫では鈍い痛みを感じる程度ですが、重度の圧迫になると、激しい痛みや麻痺といった深刻な症状が現れることもあります。
2.2 炎症の発生
飛び出した髄核は、周囲の組織に炎症を引き起こします。
この炎症もまた、足の痛みやしびれの原因となります。炎症が起きると、神経周囲の組織が腫れ上がり、神経を刺激します。
これにより、痛みが増強されるだけでなく、熱感や腫れといった症状も現れることがあります。
また、炎症物質は神経を過敏にするため、軽い刺激でも痛みを感じやすくなります。
2.3 筋肉の緊張
神経が圧迫されたり炎症が起きると、周囲の筋肉は反射的に緊張します。
この筋肉の緊張は、痛みをさらに悪化させる要因となります。
筋肉が緊張すると、血行が悪くなり、老廃物が蓄積しやすくなります。その結果、筋肉が硬くなり、痛みが増強されます。
また、筋肉の緊張は姿勢にも影響を与え、さらなる神経の圧迫や炎症を引き起こす可能性があります。
原因 | メカニズム | 症状 |
神経根への圧迫 | 飛び出した髄核が神経根を直接圧迫 | 痛み、しびれ、麻痺 |
炎症の発生 | 飛び出した髄核が周囲の組織に炎症を引き起こす | 痛み、熱感、腫れ |
筋肉の緊張 | 神経の圧迫や炎症により筋肉が反射的に緊張 | 痛み、こわばり、姿勢の変化 |
3. 椎間板ヘルニアによる足の痛みの症状

椎間板ヘルニアによって引き起こされる足の痛みは、その程度や症状が人によって大きく異なります。
神経への圧迫の程度、炎症の有無、個々の痛みの感じ方の違いなど、様々な要因が影響するためです。代表的な症状を以下にまとめました。
3.1 坐骨神経痛
椎間板ヘルニアによる足の痛みの多くは、坐骨神経痛として現れます。
坐骨神経は腰から足にかけて伸びる人体で最も太い神経であり、この神経が圧迫されることで、お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足先まで、鋭い痛みやしびれ、時には灼熱感などが走ります。
痛みは片側の足に出ることが多く、咳やくしゃみをした際に悪化することもあります。
3.2 痺れ
坐骨神経痛と同様に、しびれも椎間板ヘルニアの代表的な症状です。
足全体がしびれる場合もあれば、太ももの裏やふくらはぎの一部、足の指先など、特定の部位にしびれを感じる場合もあります。
しびれの程度も、軽いピリピリ感から、感覚がなくなるほどの強いしびれまで様々です。
また、痛みとしびれが同時に起こることも少なくありません。
3.3 感覚異常
感覚異常は、触られた感覚が鈍くなったり、逆に過敏になったりする症状です。
足の一部が常に冷たい、または熱い感じがするといった症状が現れることもあります。
また、何も触れていないのに何かが這っているような感覚(異常感覚)が生じることもあります。
3.4 筋力低下
神経が圧迫されることで、足の筋肉の力が弱くなることがあります。
つま先立ちや踵歩きが難しくなる、階段の昇降がつらい、長距離歩行が困難になるなどの症状が現れる場合もあります。
重症になると、足を引きずって歩くようになることもあります。
症状 | 説明 |
坐骨神経痛 | お尻から足にかけての痛み、しびれ、灼熱感 |
痺れ | 足全体の痺れ、または一部の痺れ |
感覚異常 | 感覚の鈍化、過敏化、冷感、熱感、異常感覚 |
筋力低下 | つま先立ち、踵歩き、階段昇降、歩行困難など |
これらの症状は、必ずしも全て同時に現れるとは限りません。
また、症状の程度も人によって大きく異なります。
少しでもこれらの症状を感じたら、早めに専門家にご相談ください。
4. 椎間板ヘルニアの診断方法
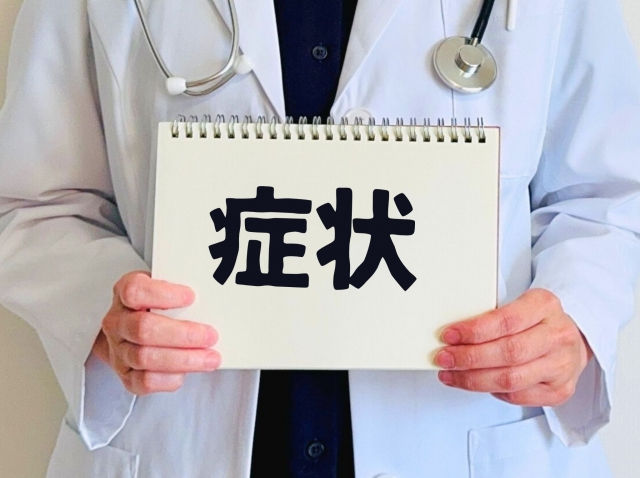
椎間板ヘルニアの診断は、丁寧な問診、詳細な身体検査、そして精密な画像検査によって行われます。
これらの組み合わせによって、痛みの原因が本当に椎間板ヘルニアなのか、他の疾患の可能性はないのかを慎重に判断します。
4.1 問診
問診では、現在の症状、痛みの程度、いつから痛み始めたのか、どのような動作で痛みが悪化するのかなど、詳しくお話を伺います。
日常生活での支障の程度や、過去の病歴、仕事内容なども重要な情報となります。
4.2 画像検査(レントゲン、MRI、CT)
画像検査は、椎間板の状態を視覚的に確認するために非常に重要です。
それぞれの検査方法の特徴を理解し、適切な検査を受けることが大切です。
検査方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
レントゲン | 骨の状態を確認する検査です。 | 被曝量が少なく、費用も比較的安価です。 | 椎間板や神経の状態までは確認できません。 |
MRI | 椎間板、神経、靭帯、脊髄など、軟部組織の状態を詳細に確認できます。 | ヘルニアの大きさや位置、神経への圧迫の程度などを正確に把握できます。 | 検査費用が高額で、検査時間も比較的長くなります。閉所恐怖症の方には不向きです。 |
CT | 骨の状態をレントゲンよりも詳細に確認できます。 | レントゲンよりも骨の状態を詳しく把握できます。 | MRIほど軟部組織の詳細は確認できません。被曝を伴います。 |
4.3 神経学的検査
神経学的検査では、神経の機能が正常に働いているかを確認します。
具体的には、筋力検査、感覚検査、反射検査などを行います。これらの検査結果から、どの神経がどの程度圧迫されているかを判断します。
下肢の筋力低下や感覚異常の程度を調べることで、ヘルニアの重症度を評価する材料にもなります。
5. 椎間板ヘルニアの一般的な治療法

椎間板ヘルニアの治療法は、症状の程度や経過、個々の状態に合わせて選択されます。
大きく分けて保存療法と手術療法の2種類があります。
5.1 保存療法
多くの椎間板ヘルニアは、保存療法で症状が改善します。
保存療法は、手術を行わずに痛みや痺れなどの症状を軽減し、日常生活への復帰を目指す治療法です。
5.1.1 薬物療法
痛みや炎症を抑えるために、次のような薬が用いられます。
薬の種類 | 作用 |
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 炎症を抑え、痛みを軽減します。ロキソニン、ボルタレンなどが代表的です。 |
ステロイド薬 | 強力な抗炎症作用があり、神経の炎症や腫れを抑えます。 |
筋弛緩薬 | 筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減します。 |
神経障害性疼痛治療薬 | 神経の損傷による痛みを軽減します。リリカ、サインバルタなどが代表的です。 |
5.1.2 理学療法
理学療法では、ストレッチや筋力トレーニング、温熱療法、牽引療法などを行い、患部の周りの筋肉を強化し、柔軟性を高めることで、痛みを軽減し、再発を予防します。
5.2 手術療法
保存療法で効果が得られない場合や、症状が重症の場合には、手術療法が検討されます。手術療法は、ヘルニアによって圧迫されている神経を解放することを目的としています。
5.2.1 主な手術方法
● 椎間板摘出術:顕微鏡や内視鏡を用いて、ヘルニアを起こしている椎間板の一部または全部を取り除く手術です。
● 椎弓切除術:椎弓と呼ばれる骨の一部を取り除き、神経の圧迫を取り除く手術です。
● 人工椎間板置換術:損傷した椎間板を人工椎間板に置き換える手術です。
手術療法は、症状の改善が期待できる一方、合併症のリスクもあるため、医師とよく相談し、慎重に判断する必要があります。
6. 鍼灸治療が椎間板ヘルニアによる足の痛みに効果的な理由

椎間板ヘルニアによる足の痛みには、保存療法や手術療法といった西洋医学的なアプローチ以外にも、鍼灸治療が効果的であると考えられています。
鍼灸治療は、身体に鍼や灸という刺激を与えることで、人間が本来持つ自然治癒力を高め、痛みや痺れなどの症状を緩和していく東洋医学に基づいた治療法です。
具体的には、以下のような効果が期待できます。
6.1 血行促進作用
鍼灸刺激は、患部周辺の血行を促進する効果があります。
血行が促進されると、酸素や栄養素が患部に届きやすくなり、損傷した組織の修復が促されます。また、老廃物の排出もスムーズになるため、炎症の抑制にも繋がります。
6.2 鎮痛作用
鍼灸治療には、エンドルフィンやエンケファリンといった鎮痛作用を持つ神経伝達物質の分泌を促進する効果があります。
これらの物質は、モルヒネの数倍もの鎮痛効果を持つと言われており、痛みを和らげるのに役立ちます。
また、鍼灸刺激が脳に伝わることで、下行性疼痛抑制系が活性化され、痛みの伝達を抑制する効果も期待できます。
6.3 筋肉の緩和作用
椎間板ヘルニアによって引き起こされる神経根の圧迫は、周囲の筋肉の緊張を高めます。
鍼灸治療は、この緊張した筋肉を緩和させる効果があります。
筋肉の緊張が緩和されると、神経根への圧迫が軽減され、痛みや痺れなどの症状が改善されます。
トリガーポイントと呼ばれる、筋肉の硬結や圧痛点に鍼灸治療を行うことで、より効果的に筋肉の緊張を緩和することができます。
6.4 神経機能の回復促進
鍼灸治療は、損傷した神経の回復を促進する効果も期待できます。
神経の伝達機能が改善されることで、痛みや痺れ、筋力低下といった症状の改善に繋がります。
また、自律神経系のバランスを整える効果もあるため、疼痛によるストレスや不安の軽減にも役立ちます。
7. 鍼灸治療のメカニズム

鍼灸治療のメカニズムは、まだ完全には解明されていませんが、次のような作用が関わっていると考えられています。
7.1 自律神経系への作用
鍼灸刺激は、自律神経系に作用し、交感神経と副交感神経のバランスを整える効果があります。
自律神経のバランスが整うことで、血行が促進され、筋肉の緊張が緩和されます。
また、リラックス効果も高まり、痛みやストレスの軽減にも繋がります。
7.2 免疫系への作用
鍼灸治療は、免疫系の活性化にも関与していると考えられています。
免疫機能が高まることで、炎症の抑制や組織の修復が促進されます。
7.3 鎮痛物質の放出
前述の通り、鍼灸刺激は、エンドルフィンやエンケファリンといった鎮痛物質の放出を促します。
これらの物質は、脳内のオピオイド受容体に結合することで、痛みの信号伝達を抑制する働きがあります。
効果 | メカニズム |
血行促進 | 患部周辺の血流改善、酸素・栄養供給促進、老廃物排出促進 |
鎮痛作用 | エンドルフィン、エンケファリンなどの鎮痛物質分泌促進、下行性疼痛抑制系の活性化 |
筋肉の緩和 | 筋肉の緊張緩和、神経根への圧迫軽減、トリガーポイントへの刺激 |
神経機能の回復促進 | 神経伝達機能改善、自律神経バランス調整 |
8. 鍼灸治療のメカニズム

鍼灸治療が椎間板ヘルニアによる足の痛みに対してどのように効果を発揮するのか、そのメカニズムについて詳しく解説します。
8.1 自律神経系への作用
鍼灸治療は、自律神経系に作用することで、痛みを緩和すると考えられています。
自律神経系は、交感神経と副交感神経から成り立っており、体の機能を調節する重要な役割を担っています。
ストレスや緊張状態が続くと交感神経が優位になり、筋肉が緊張しやすくなります。その結果、血行不良や痛みが悪化することがあります。
鍼灸刺激は、副交感神経を活性化させることで、リラックス効果を高め、交感神経の緊張を和らげます。
これにより、筋肉の緊張が緩和され、血行が促進され、痛みの軽減につながると考えられています。
8.2 免疫系への作用
鍼灸治療は、免疫系にも作用すると考えられています。
鍼灸刺激によって、白血球の一種であるリンパ球の活性化が促進され、免疫機能の向上が期待できます。
免疫機能の向上は、炎症の抑制や組織の修復を促進する効果があり、椎間板ヘルニアによる足の痛みの改善に役立つと考えられています。
8.3 鎮痛物質の放出
鍼灸治療は、体内で鎮痛物質の放出を促進する効果があるとされています。
鍼灸刺激により、エンドルフィンやエンケファリンなどの鎮痛作用を持つ神経伝達物質が放出されます。
これらの物質は、モルヒネの数倍もの鎮痛効果を持つと言われており、痛みを和らげる効果が期待できます。
また、セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質の分泌も促進され、精神的なリラックス効果も期待できます。
これらの作用が相まって、椎間板ヘルニアによる足の痛みを効果的に緩和すると考えられています。
メカニズム | 作用 | 効果 |
自律神経系への作用 | 副交感神経の活性化、交感神経の抑制 | 筋肉の緊張緩和、血行促進、痛みの軽減 |
免疫系への作用 | リンパ球の活性化、免疫機能の向上 | 炎症の抑制、組織の修復促進 |
鎮痛物質の放出 | エンドルフィン、エンケファリン、セロトニン、ドーパミンの放出 | 鎮痛効果、精神的なリラックス効果 |
これらのメカニズムが複雑に絡み合い、鍼灸治療は椎間板ヘルニアによる足の痛みに対して多角的にアプローチすることで、症状の改善を促すと考えられています。
9. 椎間板ヘルニアの予防法

椎間板ヘルニアは、一度発症すると再発のリスクも抱えるため、日頃から予防を心がけることが重要です。ここでは、椎間板ヘルニアの予防に効果的な方法をいくつかご紹介します。
9.1 正しい姿勢を保つ
不良姿勢は椎間板への負担を増大させ、ヘルニア発症のリスクを高めます。 デスクワークやスマートフォンの操作など、長時間同じ姿勢を続ける場合は、こまめに休憩を取り、姿勢を正すように意識しましょう。具体的には、背筋を伸ばし、顎を引いて、目線をまっすぐに向けることが大切です。椅子に座る際は、深く腰掛け、背もたれに背中を付けるようにしましょう。また、足を組む癖がある方は、足を組まないように注意してください。
9.2 適度な運動を行う
適度な運動は、背骨周りの筋肉を強化し、椎間板への負担を軽減する効果があります。 ウォーキングや水泳など、体に負担の少ない有酸素運動がおすすめです。腰に負担がかかりやすい激しい運動や、急に体をひねる運動は避けましょう。運動を行う際は、事前に準備運動を行い、体に無理のない範囲で行うようにしてください。また、運動中に痛みを感じた場合は、すぐに中止しましょう。
9.3 ストレッチで柔軟性を高める
ストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、血行を促進する効果があります。 柔軟性を高めることで、椎間板への負担を軽減し、ヘルニアの予防につながります。特に、腰回りや股関節周りのストレッチは効果的です。毎日継続して行うことで、より効果を実感できます。下記に具体的なストレッチの例を挙げます。
ストレッチ | 方法 | 回数 |
ハムストリングスストレッチ | 足を伸ばして座り、片方の足を軽く曲げ、もう片方の足のかかとを持ち、息を吐きながら上体を前に倒します。 | 左右10回ずつ |
大腰筋ストレッチ | 片方の足を大きく前に出し、もう片方の足の膝を床につけ、息を吐きながら上体を前に倒します。 | 左右10回ずつ |
梨状筋ストレッチ | 仰向けに寝て、片方の足をもう片方の足の太ももに乗せ、息を吐きながら両手で太ももを抱え込みます。 | 左右10回ずつ |
これらのストレッチは、腰痛予防にも効果的です。無理のない範囲で行い、痛みを感じた場合は中止してください。
上記以外にも、体重管理も椎間板ヘルニアの予防に重要です。
過度な体重は椎間板への負担を増大させるため、適正体重を維持するように心がけましょう。バランスの良い食事と適度な運動を組み合わせ、健康的な生活習慣を送りましょう。
10. まとめ

椎間板ヘルニアによる足の痛みは、神経根の圧迫や炎症、筋肉の緊張などが原因で起こります。
坐骨神経痛や痺れ、感覚異常、筋力低下といった症状が現れる場合もあります。診断には問診、画像検査、神経学的検査などが用いられます。
一般的な治療法には保存療法や手術療法がありますが、鍼灸治療も効果が期待できます。
鍼灸治療は血行を促進し、痛みを鎮め、筋肉を緩和することで、神経機能の回復を促すと考えられています。
これは自律神経系や免疫系への作用、鎮痛物質の放出といったメカニズムによるものと考えられています。
さらに、正しい姿勢や適度な運動、ストレッチなどで椎間板ヘルニアを予防することも大切です。
お困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
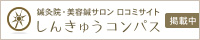




コメント