椎間板ヘルニアによる足のむくみ:原因と関係、鍼灸治療の効果とは?
- 鍼灸院 横浜文庫
- 7月10日
- 読了時間: 15分

足のむくみ、気になりますよね? 特に、椎間板ヘルニアがある方は、そのむくみがヘルニアと関係しているのではないかと不安になるかもしれません。
この記事では、椎間板ヘルニアと足のむくみの関係性について、その原因やメカニズムを分かりやすく解説します。
さらに、放置した場合のリスクや一般的な対処法に加え、鍼灸治療がどのように足のむくみにアプローチするのかについても詳しくご説明します。
この記事を読むことで、足のむくみの原因を理解し、適切な対処法を見つけるための一助となるでしょう。そして、日々の生活の中で実践できる予防策を知ることで、将来の足のむくみを軽減できる可能性があります。
1. 椎間板ヘルニアとは何か

椎間板ヘルニアは、腰や首に起こる代表的な疾患の一つです。
多くの人が悩まされているこの症状は、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。
一体どのようなメカニズムで発症するのでしょうか。まずは椎間板の構造と役割から理解を深めていきましょう。
1.1 椎間板の構造と役割
椎間板は、背骨を構成する椎骨と椎骨の間に位置するクッションのような組織です。
弾力性があり、衝撃を吸収することで、身体の動きをスムーズにする役割を担っています。この椎間板は、中心部にゼリー状の髄核と、それを囲む線維輪という組織で構成されています。
構成要素 | 役割 |
髄核 | 水分を多く含み、弾力性と柔軟性を持つ。衝撃吸収の役割を担う。 |
線維輪 | 髄核を包み込むように構成されている。コラーゲン線維でできており、髄核を支え、飛び出さないようにする役割を持つ。 |
この髄核と線維輪の構造が、椎間板ヘルニアの発症に大きく関わっています。
1.2 椎間板ヘルニアの発生メカニズム
椎間板ヘルニアは、加齢や姿勢の悪さ、過度な負担などによって、線維輪に亀裂が生じ、中の髄核が飛び出すことで発症します。
この飛び出した髄核が神経を圧迫することで、痛みやしびれなどの症状が現れます。
椎間板ヘルニアは、発生する部位によって、頸椎椎間板ヘルニアと腰椎椎間板ヘルニアに分けられます。
腰椎椎間板ヘルニアは、足の痛みやしびれ、腰痛などの症状を引き起こし、頸椎椎間板ヘルニアは、首や肩の痛み、腕のしびれなどの症状を引き起こします。
また、ヘルニアの突出方向や程度によっても症状は様々です。
軽度のヘルニアであれば、自然に症状が改善することもありますが、重症化すると手術が必要になる場合もあります。そのため、早期の診断と適切な治療が重要です。
2. 椎間板ヘルニアと足のむくみの関係

椎間板ヘルニアが足のむくみを引き起こすメカニズムは、主に神経圧迫による血流・リンパ流の阻害、炎症による組織の腫脹、そして痛みによる運動不足の3つの要素が複雑に絡み合っています。
これらが単独で、あるいは複数組み合わさってむくみを生じさせます。
2.1 神経圧迫による血流・リンパ流の阻害
椎間板ヘルニアになると、飛び出した椎間板が神経根や馬尾神経を圧迫します。
この圧迫は、神経周辺の血管やリンパ管にも影響を及ぼし、血流やリンパ流を阻害します。
その結果、静脈血やリンパ液が滞り、足にむくみが生じやすくなります。
特に、ヘルニアが腰部に発生した場合、下半身への影響が大きく、足のむくみが顕著に現れることがあります。
圧迫部位 | 影響 |
神経根 | 神経根に沿って分布する領域の血流・リンパ流が阻害され、対応する領域に沿ってむくみが生じることがあります。 |
馬尾神経 | 両足にむくみが生じることがあります。排尿・排便障害を伴うこともあります。 |
2.2 炎症による組織の腫脹
ヘルニアによって神経が圧迫されると、その周囲に炎症が生じます。
炎症反応は、患部周辺の組織に腫れを引き起こし、これがむくみとして認識されることがあります。
また、炎症によって産生される物質が、さらに血管透過性を高め、むくみを増悪させる可能性もあります。
この炎症は、神経根だけでなく、周囲の筋肉や軟部組織にも波及し、より広範囲のむくみを引き起こす場合もあります。
2.3 痛みによる運動不足
椎間板ヘルニアによる痛みは、しばしば激しいものです。
この痛みによって、歩行や運動が制限され、活動量が低下します。
すると、筋肉のポンプ作用が弱まり、静脈血やリンパ液の還流が滞り、足のむくみが助長されます。
特に、下肢の運動不足は、重力によって体液が足に溜まりやすくなるため、むくみを悪化させる大きな要因となります。
痛みを我慢して無理に動くと症状が悪化する可能性もあるため、適切な運動療法の指導を受けることが重要です。
3. 椎間板ヘルニアによる足のむくみの原因

椎間板ヘルニアによって足のむくみが引き起こされる原因は、大きく分けて「神経根への圧迫」と「馬尾症候群」の2つが考えられます。
これらは症状の重さや範囲に影響を与えます。 どちらの場合も、適切な対処が必要となるため、足のむくみを感じたら早めに専門家へ相談することが重要です。
3.1 神経根への圧迫
椎間板ヘルニアは、椎間板の中にある髄核という組織が飛び出すことで、周囲の神経を圧迫します。
この神経の中には、足の感覚や運動を司る神経も含まれており、圧迫されることで様々な症状が現れます。
神経根が圧迫されると、血流やリンパの流れが滞り、老廃物が下肢に溜まりやすくなります。
これが足のむくみの原因の一つです。
また、神経の炎症もむくみを悪化させる要因となります。
さらに、神経圧迫による痛みは、運動不足につながり、これもまたむくみを助長する可能性があります。
圧迫される神経根 | 影響を受ける部位 | 症状 |
L4 | 太ももの前側、内側 | 膝蓋腱反射の低下、つま先立ちが困難 |
L5 | 下腿の外側、足の甲 | 足関節の背屈が困難 |
S1 | 下腿の後面、足の裏 | アキレス腱反射の低下、かかと立ちが困難 |
上記のように、どの神経根が圧迫されるかによって、むくみだけでなく、痛みやしびれの出現する場所も異なります。
そのため、症状の出方からどの神経根が圧迫されているかを推測することができます。
3.2 馬尾症候群
馬尾症候群は、複数の神経根が圧迫されることで、膀胱直腸障害(排尿・排便障害)などの重篤な症状を引き起こす疾患です。
神経根への圧迫が重度になると、馬尾症候群を発症するリスクが高まります。
馬尾症候群では、両足のしびれや脱力、会陰部の異常感覚 などが現れます。
また、進行すると膀胱や直腸の機能が麻痺し、排尿・排便のコントロールが困難になることもあります。
これらの症状に加えて、足のむくみも現れることがあります。
馬尾症候群は緊急性を要する疾患であるため、疑わしい症状が現れた場合は、すぐに専門家へ相談することが重要です。
馬尾症候群は、放置すると後遺症が残る可能性もあるため、早期発見・早期治療が非常に重要です。
4. 椎間板ヘルニアによる足のむくみを放置するリスク

椎間板ヘルニアによる足のむくみは、放置すると様々なリスクを招きます。
初期症状では軽度のむくみや違和感程度で済む場合もありますが、進行すると日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
早期に適切な対処をすることが重要です。
4.1 慢性的な痛み
椎間板ヘルニアによる足のむくみを放置すると、神経への圧迫が継続し、慢性的な痛みに悩まされる可能性があります。
初期は間欠的な痛みでも、次第に持続的な痛みへと変化し、安静時にも痛みを感じるようになります。
慢性的な痛みは、日常生活の質を著しく低下させるため、早期の対処が重要です。
4.2 痺れの悪化
足のむくみと共に痺れを感じている場合、放置することで痺れが悪化する可能性があります。
神経への圧迫が強まることで、痺れの範囲が広がったり、感覚が鈍くなったりすることがあります。
また、進行すると、足に力が入りにくくなることもあり、歩行困難に陥るケースも少なくありません。日常生活に支障が出ないよう、早めの対策が必要です。
4.3 日常生活への支障
椎間板ヘルニアによる足のむくみは、日常生活に様々な支障をきたします。
痛みや痺れによって、歩行や階段の上り下りが困難になるだけでなく、長時間の座位や立位も辛くなります。
また、靴が履けなくなったり、足の爪切りが難しくなるなど、日常生活の些細な動作にも影響を及ぼすことがあります。
症状が進行する前に、適切な治療を受けることが大切です。
4.4 排尿・排便障害
ヘルニアが腰椎で発生し、馬尾神経を圧迫している場合、放置すると排尿・排便障害を引き起こす可能性があります。
尿意や便意を感じにくくなったり、逆に失禁してしまうこともあります。
これは、馬尾症候群と呼ばれる深刻な症状であり、緊急性の高い状態です。
このような症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診する必要があります。
放置のリスク | 具体的な症状 | 影響 |
慢性的な痛み | 安静時痛、持続的な痛み | 日常生活の質の低下、睡眠障害 |
痺れの悪化 | 痺れの範囲拡大、感覚鈍麻、筋力低下 | 歩行困難、転倒リスクの増加 |
日常生活への支障 | 歩行困難、階段昇降困難、座位・立位困難、着替え困難 | 仕事や家事への支障、社会活動の制限 |
馬尾症候群 | 排尿・排便障害、下肢の麻痺、性機能障害 | 緊急手術が必要な場合あり、後遺症が残る可能性 |
これらのリスクを避けるためにも、足のむくみや痛み、痺れを感じたら、早めに専門家へ相談し、適切な治療を受けることが重要です。
自己判断で放置せず、症状が悪化する前に対応しましょう。
5. 椎間板ヘルニアによる足のむくみの一般的な治療法

椎間板ヘルニアによる足のむくみの治療法は、症状の程度や個々の状態に合わせて選択されます。
大きく分けて保存療法と手術療法の2種類があり、多くの場合はまず保存療法が試みられます。
5.1 保存療法
保存療法は、手術をせずに痛みやむくみなどの症状を軽減することを目的とした治療法です。
具体的には、薬物療法、理学療法などがあります。
5.1.1 薬物療法
痛みや炎症を抑えるために、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や鎮痛剤が処方されることがあります。
また、神経の炎症や痛みを抑えるために、神経障害性疼痛治療薬が使用される場合もあります。
むくみが強い場合には、利尿剤が使用されることもあります。
これらの薬剤は、患者の状態に合わせて適切に選択・調整されます。
5.1.2 理学療法
理学療法では、ストレッチや筋力トレーニングなどを通して、患部の周りの筋肉を強化し、姿勢を改善することで、症状の緩和を目指します。
温熱療法や寒冷療法なども用いられることがあります。
理学療法士の指導のもと、個々の状態に合わせた適切な運動プログラムが作成されます。
5.2 手術療法
保存療法で効果が得られない場合や、症状が重症の場合には、手術療法が検討されます。
手術療法にはいくつかの種類がありますが、代表的なものとして、椎間板ヘルニア摘出術や内視鏡下手術などがあります。
手術の種類 | 概要 | メリット | デメリット |
椎間板ヘルニア摘出術 | ヘルニアを起こしている椎間板の一部または全部を切除する手術 | ヘルニアによる神経圧迫を直接的に取り除くことができる | 侵襲が比較的大きい、入院期間が長くなる場合がある |
内視鏡下手術 | 小さな切開部から内視鏡を挿入し、ヘルニアを切除する手術 | 侵襲が小さい、術後の回復が早い | すべての症例に適応できるわけではない |
レーザー治療 | レーザーを用いて椎間板内の水分を蒸発させ、ヘルニアの縮小を促す治療 | 侵襲が小さい、日帰りで行える場合もある | 効果が限定的である場合がある |
手術療法は、患者さんの状態やヘルニアの程度によって適切な方法が選択されます。
どの手術にもメリット・デメリットがあるため、担当医とよく相談し、理解した上で手術を受けることが重要です。
6. 鍼灸治療が椎間板ヘルニアによる足のむくみに効果的な理由

椎間板ヘルニアによる足のむくみは、神経圧迫による血流やリンパ流の滞り、炎症、痛みによる運動不足などが原因で起こります。
これらの症状に対して、鍼灸治療は多角的なアプローチで効果を発揮することが期待できます。
6.1 血流改善効果
鍼灸治療は、局所の血流を改善する効果があります。
鍼を刺入することで、皮膚や筋肉に微細な損傷が生じ、体がそれを修復しようと働きかけます。
この過程で、血管が拡張し、血流が促進されます。
血流が良くなることで、滞っていた老廃物や炎症物質が排出され、むくみが軽減されます。また、酸素や栄養素が患部に届きやすくなるため、組織の修復も促されます。
6.2 鎮痛効果
椎間板ヘルニアによる足のむくみは、しばしば痛みを伴います。
鍼灸治療は、鎮痛効果も期待できます。
鍼刺激によって、エンドルフィンやエンケファリンなどの鎮痛物質が分泌され、痛みが緩和されます。
また、鍼灸治療は、ゲートコントロールセオリーに基づき、痛み信号の伝達を抑制する効果も持っています。
痛みを和らげることで、より積極的に動くことができ、むくみの改善につながります。
6.3 筋肉の緊張緩和
神経圧迫や痛みによって、足の筋肉が緊張し、血流やリンパ流の悪化につながるケースも少なくありません。
鍼灸治療は、筋肉の緊張を緩和する効果があります。
鍼を筋肉に刺入することで、筋肉の過剰な緊張が解け、血流やリンパ流がスムーズになります。
また、トリガーポイントと呼ばれる筋肉の硬結部位に鍼を刺入することで、より効果的に筋肉の緊張を緩和し、痛みやむくみを軽減することができます。
6.4 自律神経調整効果
自律神経の乱れも、足のむくみに影響を与えることがあります。
鍼灸治療は、自律神経のバランスを整える効果も期待できます。
鍼刺激によって、副交感神経が優位になり、リラックス効果が高まります。
自律神経のバランスが整うことで、血流やリンパ流の調整機能が正常化し、むくみの改善に繋がります。
また、自律神経が整うことで、睡眠の質の向上やストレス軽減にも効果が期待できます。これらの効果も間接的にむくみの改善に貢献します。
効果 | メカニズム |
血流改善 | 血管拡張、老廃物排出促進 |
鎮痛効果 | エンドルフィン分泌、ゲートコントロールセオリー |
筋肉の緊張緩和 | トリガーポイントへの刺激 |
自律神経調整 | 副交感神経優位、リラックス効果 |
鍼灸治療は、これらの効果を通して、椎間板ヘルニアによる足のむくみを総合的に改善へと導きます。ただし、症状や体質によって効果の出方には個人差があります。鍼灸師とよく相談しながら、治療を進めていくことが大切です。
7. 椎間板ヘルニアによる足のむくみの予防法

椎間板ヘルニアによる足のむくみを予防するためには、日常生活における姿勢や運動、体重管理などに気を配ることが重要です。
日頃から意識的に予防に取り組むことで、ヘルニアの発症や再発リスクを低減し、快適な生活を送ることができます。
7.1 正しい姿勢
不良姿勢は椎間板に負担をかけ、ヘルニアを引き起こす要因の一つです。
特に、猫背や前かがみの姿勢は腰椎への負担を増大させます。
デスクワークやスマートフォンの操作など、長時間同じ姿勢を続ける場合は、こまめに休憩を取り、背筋を伸ばすストレッチを行うようにしましょう。
7.1.1 座り姿勢
椅子に座るときは、浅く座らず、深く腰掛け、背もたれに背中をしっかりとつけるように心がけてください。
また、足を組む癖がある方は、骨盤の歪みにつながるため、意識的に足を組まないようにしましょう。
デスクワークを行う際は、椅子の高さやモニターの位置を調整し、無理のない姿勢を保つことが大切です。クッションやサポート器具を使用することも有効です。
7.1.2 立ち姿勢
立つ際は、背筋を伸ばし、お腹を軽く引き締めることを意識しましょう。
また、長時間同じ場所に立っている場合は、適度に足を動かしたり、体重を左右の足に交互にかけたりすることで、腰への負担を軽減できます。
7.1.3 持ち上げ姿勢
重い物を持ち上げる際は、膝を曲げて腰を落とすようにし、腰に負担がかからないように注意してください。
背中を丸めたまま持ち上げると、椎間板に大きな負担がかかり、ヘルニアのリスクを高める可能性があります。
7.2 適度な運動
適度な運動は、腰周りの筋肉を強化し、椎間板への負担を軽減する効果があります。
ウォーキングや水泳など、腰に負担の少ない運動を継続的に行うことが大切です。
ただし、激しい運動や急に無理な姿勢をとる運動は、逆に症状を悪化させる可能性があるので避けましょう。
7.2.1 ウォーキング
ウォーキングは、特別な道具や場所を必要とせず、手軽に取り組める有酸素運動です。
正しい姿勢を意識し、30分程度を目安に、毎日継続して行うことが理想的です。
無理のないペースで、自分の体力に合わせた距離や時間を設定しましょう。
7.2.2 水泳
水泳は、浮力によって腰への負担が軽減されるため、椎間板ヘルニアの予防に適した運動です。
特に、クロールや背泳ぎは、腰周りの筋肉をバランス良く鍛える効果があります。水中ウォーキングも効果的です。
7.2.3 ストレッチ
ストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、血行を促進する効果があります。
腰痛予防に効果的なストレッチを、朝晩など習慣的に行うようにしましょう。入浴後など、体が温まっている時に行うとより効果的です。
運動の種類 | 効果 | 注意点 |
ウォーキング | 手軽にできる有酸素運動、腰への負担が少ない | 正しい姿勢を意識する、無理のないペースで行う |
水泳 | 浮力により腰への負担が少ない、全身運動 | 水温に注意する、無理のない距離や時間で行う |
ストレッチ | 筋肉の柔軟性向上、血行促進 | 反動をつけずにゆっくり行う、痛みを感じる場合は中止する |
7.3 体重管理
過剰な体重は、椎間板への負担を増大させるため、適正体重を維持することが重要です。
バランスの良い食事と適度な運動を心がけ、肥満を予防しましょう。特に、お腹周りの脂肪は腰への負担を増大させるため、内臓脂肪を減らすことを意識した食生活を心がけることが大切です。
これらの予防法を実践することで、椎間板ヘルニアによる足のむくみを予防し、健康な身体を維持することができます。日々の生活習慣を見直し、積極的に予防に取り組みましょう。
8. まとめ

椎間板ヘルニアによる足のむくみは、神経圧迫による血流やリンパ流の阻害、炎症、痛みによる運動不足などが原因で起こります。
放置すると慢性的な痛みやしびれの悪化につながるため、早期の対処が必要です。
一般的な治療法には、薬物療法、理学療法、牽引療法などの保存療法や、手術療法があります。
鍼灸治療は、血流改善、鎮痛、筋肉の緊張緩和、自律神経調整効果などにより、足のむくみの改善に効果が期待できます。
さらに、日頃から正しい姿勢を保つ、適度な運動をする、体重管理を心がけることで、椎間板ヘルニアによる足のむくみを予防することができます。
何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
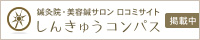




コメント